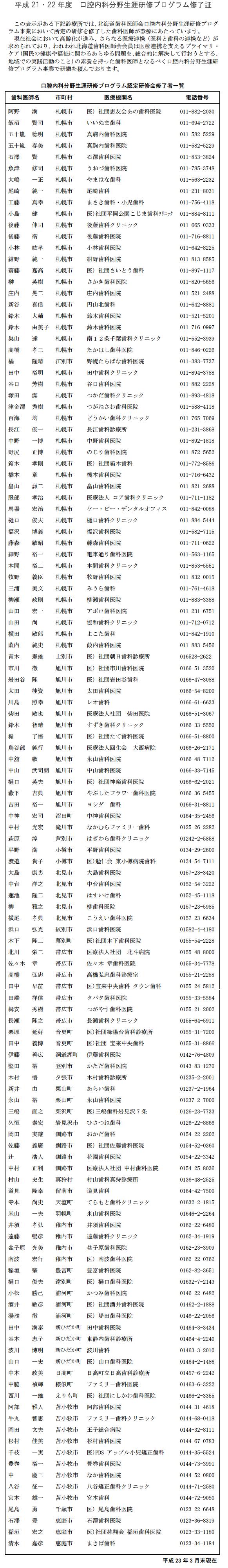避難所暮らしで気をつけなければならないのは、水や歯磨き粉不足から十分な歯磨きができず、口の中で細菌が繁殖してインフルエンザや肺炎、胃腸炎といった感染症を引き起こすことだ。
高齢者にとって怖いのが「誤嚥性肺炎」だ。細菌の多い唾液や食べ物などが誤って気管に入って起こる。町立山田南小学校の避難所では震災から7日目、歯磨きを十分せず、誤嚥性肺炎をおこして病院に運び込まれた高齢者の男性がいた。
入れ歯の手入れにも注意が必要だ。就寝前には入れ歯を必ず外し、歯ブラシを細かく動かして磨く。入れ歯に熱湯を注ぐ人もいるが、変形して装着できなくなる恐れがあるのでやめる。誤嚥防止のために、口の周りの筋肉を鍛える方法もある。「あ」「い」「う」と大きく口を開けて1日10回以上声を出したり、舌を前や左右に最低10秒突き出したりする。
読売新聞 2011.3.30
記事一覧
震災の現場から 口内ケアで感染症予防
訪問歯科診療の今後の新しい姿 戸原 玄
訪問歯科診療にかかわっている方であればよく感じると思いますが、患者さんやご家族、主治医の先生方からの要望は、実のところ”歯を治してほしい”というものではなく”食べられるようにしてほしい”というものが多いのです。
「噛めない、飲み込めない」という状態は、もちろん歯だけの問題ではありません。歯科治療と並行して摂食・嚥下機能を専門的にみていくことが、今後の訪問歯科治療のあるべき姿であると考えます。
VE(嚥下内視鏡検査)による精査を行ったうえで、安全に食べられる食形態・量・姿勢を評価しています。ご家族へ指導を行う際には、このようにできるだけ具体的で明確に伝えられる指導が大切なのです。摂食・嚥下障害のある患者さんに適切かつ具体的な指導を、自信をもって行うためには、患者さんに精査を受けてもらえる環境を確保することが大切です。
口腔ケアをするとき、患者さんの姿勢に目を向けよう!
看護師のYさんは、脳梗塞の後遺症で認知に障害がある70代女性の患者さん
を担当しています。その方は車椅子に座って自分でご飯を食べ、歯磨きもできま
す。ただ、いつも食事や歯磨きの最後になるとゴホゴホとむせてしまうことが気
になっていました。
そこでいつも患者さんの口元や手の動きばかり見ていたのを、少し引いて患者
さんの全体を見るようにしたのです。すると、あることに気づきました。
「あっ! 姿勢がだんだん左の方に傾いている……」
左半身に麻痺のある患者さんは、動きが鈍くなる左側へと姿勢が少しずつ崩れ
ていたのです。患者さんの姿勢をきちんと直してあげたところ、むせることがほ
とんどなくなりました。
これまでは寝たきりの患者さんのほうが手も目もかけなければならないため、
気をつけて見ていたというYさん。今回の出来事をきっかけに、自分の意志で体
を動かせる患者さんにも同じように注意を払わなければいけないことを、再確認
できたといいます。
Yさんのように、半介助が必要な患者さんの“姿勢”を一度見直してみるとよ
いかもしれません。
被災開業医に休業補償を
自民党の厚生労働部会(田村憲久部会長)は、4月27日、東日本大震
災の復旧を支援する2011年度 第1回補正予算案について、厚生
労働省からヒアリングを行った。その中で石井みどり参院議員は、
原発事故で避難を強いられている(福島県双葉町と同樽葉町の)歯
科診療所から寄せられた声を紹介した。"労働者向けの支援は(補
正予算案に)あるが、雇用主には何の支援もない。これでは医院の
経営はできない。いつ戻れるか分からず、見通しもない。こうい
う人に対して国はどういう支援をしてくれるのか、という声が寄
せられている。」と述べた。田村部会長も「問題意識を持たねば
ならない。全ての事業主に共通する問題で、経済産業省ともよく
相談してほしい。」と求めた。
身元確認に北海道歯科医師会会員派遣
日歯より4月28日に、岩手県における身元確認作業に関しての依頼
があり、本会より8名の先生方(札幌3名、室蘭2名、十勝1名、留萌
1名、後志1名)が派遣されることになった。5月13日より17日まで
第1班として4名、さらに5月16日より20日まで第2班として4名の先
生方が岩手県に滞在し作業を行う。実際の身元確認作業は、第1班
が14日~16日、第2班が17日~19日、各々3日間である。
現在、歯科医療従事者派遣(ボランティア)登録者は79名(歯科医師
60名、歯科衛生士15名、歯科助手1名、歯科技工士3名)、身元確認
作業派遣登録者は129名となっております。
歯 培養液で土台再生、名古屋大のチーム成功 幹細胞、移植せず
臓器や骨などのもとになる幹細胞の培養液を使い、ヒトの歯を支えるあごの骨(歯槽骨(しそうこつ))を再生することに、上田実・名古屋大教授(顎(がく)顔面外科)らのチームが成功した。幹細胞を移植する方法より安全で効率的な治療として注目される。6月に京都市で開かれる日本炎症・再生医学会で発表する。
歯周病や抜歯で歯を失うと、歯の土台となる歯槽骨が小さくなり、歯の再建が難しくなる。自分の骨や人工骨を移植するなどの方法があるが、手術時の負担が大きい。
チームは、ヒトの骨髄幹細胞を培養した液の上澄みを濃縮し、その粉末を精製水に溶かしたものを、左上の奥歯が欠損した40代女性の患部に、インプラント(人工歯根)とともに移植した。
その結果、歯槽骨が再生し、女性は約5カ月後には硬いものも食べられるようになった。チームは以前、幹細胞を移植することによって歯槽骨を再生させることにも成功しているが、幹細胞にはがん化の危険性があるため、より安全な治療法を模索していた。
幹細胞そのものでなくても骨が再生するメカニズムについてチームは、幹細胞に含まれるたんぱく質が培養液に溶け出し、そのたんぱく質の働きによって、体内にもともとある幹細胞による骨の再生が促されたとみている。上田教授は「幹細胞移植を伴わなければ、細胞を培養する施設運営のコストや、極めて厳格な管理が不要になり、治療の実用化が容易になる」と話す。
2011年5月10日 提供:毎日新聞社
在宅歯科医療連携室を設置
在宅歯科医療を推進するため、▽医科・介護等との連携窓口及び在宅歯科医療希望者等の窓口の設置▽在宅歯科医療や口腔ケア指導等の実施歯科診療所の紹介
▽在宅歯科医療に対する広報▽在宅歯科医療機器の貸し出しーなどを行っている。奈良県歯では平成19年度から在宅歯科医療実施診療所を増やすための講演会を年1回開催しており、昨年度は県医療対策部地域医療連携課の協力により、公開講座として開催。
病院、訪問看護事業所、介護施設、地域包括支援センター等に広く周知するとともに、歯科医師、歯科衛生士だけでなく、看護師、言語聴覚士、栄養士、ケアマネジャー、介護職にも参加を呼びかけ、多数の参加を得た。
また、同じく平成19年度より、訪問歯科衛星指導ができるしか衛生士を養成するため、講演だけでなく介護施設での実習を取り入れた、4日間の講座を開催している。昨年度からはさらにアドバンスコース(3日間)も開催し、人的養成に力を入れている。
さらに本年2月には、県老人福祉施設協議会職員研究会議に県歯の連携室運営メンバーがシンポジストとして参加し、高齢者の口腔ケアの重要性とその効果について講演した他、広報用リーフレットとして『あなたのお家で歯の治療』を制作し、会員診療所や関係各所に配布している。
在宅歯科医療連携室には専任職員として歯科衛生士を配置し、在宅歯科医療の希望者に対する訪問歯科診療・訪問口腔ケアが可能な診療所の紹介だけでなく、病院や介護施設、ケアマネジャー等からの養成により、出張で口腔ケアの指導・説明や相談に対応できるようにしている。
日歯広報
過去ログ
- 2026年02月 (17件)
- 2026年01月 (31件)
- 2025年12月 (26件)
- 2025年11月 (24件)
- 2025年10月 (26件)
- 2025年09月 (20件)
- 2025年08月 (22件)
- 2025年07月 (21件)
- 2025年06月 (12件)
- 2025年05月 (13件)
- 2025年04月 (5件)
- 2025年03月 (11件)
- 2025年02月 (11件)
- 2025年01月 (13件)
- 2024年12月 (22件)
- 2024年11月 (22件)
- 2024年10月 (20件)
- 2024年09月 (17件)
- 2024年08月 (24件)
- 2024年07月 (16件)
- 2024年06月 (13件)
- 2024年05月 (23件)
- 2024年04月 (17件)
- 2024年03月 (13件)
- 2024年02月 (19件)
- 2024年01月 (16件)
- 2023年12月 (27件)
- 2023年11月 (17件)
- 2023年10月 (14件)
- 2023年09月 (17件)
- 2023年08月 (17件)
- 2023年07月 (16件)
- 2023年06月 (18件)
- 2023年05月 (14件)
- 2023年04月 (16件)
- 2023年03月 (20件)
- 2023年02月 (14件)
- 2023年01月 (12件)
- 2022年12月 (21件)
- 2022年11月 (16件)
- 2022年10月 (17件)
- 2022年09月 (17件)
- 2022年08月 (16件)
- 2022年07月 (15件)
- 2022年06月 (20件)
- 2022年05月 (10件)
- 2022年04月 (14件)
- 2022年03月 (22件)
- 2022年02月 (15件)
- 2022年01月 (17件)
- 2021年12月 (18件)
- 2021年11月 (13件)
- 2021年10月 (24件)
- 2021年09月 (16件)
- 2021年08月 (17件)
- 2021年07月 (20件)
- 2021年06月 (14件)
- 2021年05月 (15件)
- 2021年04月 (20件)
- 2021年03月 (22件)
- 2021年02月 (10件)
- 2021年01月 (10件)
- 2020年12月 (15件)
- 2020年11月 (15件)
- 2020年10月 (16件)
- 2020年09月 (15件)
- 2020年08月 (19件)
- 2020年07月 (15件)
- 2020年06月 (14件)
- 2020年05月 (19件)
- 2020年04月 (12件)
- 2020年03月 (9件)
- 2020年02月 (18件)
- 2020年01月 (14件)
- 2019年12月 (23件)
- 2019年11月 (11件)
- 2019年10月 (15件)
- 2019年09月 (20件)
- 2019年08月 (12件)
- 2019年07月 (19件)
- 2019年06月 (19件)
- 2019年05月 (14件)
- 2019年04月 (11件)
- 2019年03月 (14件)
- 2019年02月 (10件)
- 2019年01月 (5件)
- 2018年12月 (16件)
- 2018年11月 (15件)
- 2018年10月 (15件)
- 2018年09月 (16件)
- 2018年08月 (6件)
- 2018年07月 (32件)
- 2018年06月 (17件)
- 2018年05月 (11件)
- 2018年04月 (24件)
- 2018年03月 (14件)
- 2018年02月 (8件)
- 2018年01月 (17件)
- 2017年12月 (15件)
- 2017年11月 (26件)
- 2017年10月 (22件)
- 2017年09月 (30件)
- 2017年08月 (24件)
- 2017年07月 (14件)
- 2017年06月 (27件)
- 2017年05月 (10件)
- 2017年04月 (23件)
- 2017年03月 (21件)
- 2017年02月 (14件)
- 2017年01月 (31件)
- 2016年12月 (25件)
- 2016年11月 (18件)
- 2016年10月 (17件)
- 2016年09月 (15件)
- 2016年08月 (9件)
- 2016年07月 (10件)
- 2016年06月 (19件)
- 2016年05月 (10件)
- 2016年04月 (13件)
- 2016年03月 (13件)
- 2016年02月 (14件)
- 2016年01月 (15件)
- 2015年12月 (26件)
- 2015年11月 (31件)
- 2015年10月 (31件)
- 2015年09月 (37件)
- 2015年08月 (40件)
- 2015年07月 (37件)
- 2015年06月 (40件)
- 2015年05月 (33件)
- 2015年04月 (33件)
- 2015年03月 (29件)
- 2015年02月 (32件)
- 2015年01月 (27件)
- 2014年12月 (29件)
- 2014年11月 (27件)
- 2014年10月 (31件)
- 2014年09月 (34件)
- 2014年08月 (34件)
- 2014年07月 (35件)
- 2014年06月 (48件)
- 2014年05月 (42件)
- 2014年04月 (38件)
- 2014年03月 (43件)
- 2014年02月 (38件)
- 2014年01月 (37件)
- 2013年12月 (43件)
- 2013年11月 (41件)
- 2013年10月 (44件)
- 2013年09月 (44件)
- 2013年08月 (41件)
- 2013年07月 (33件)
- 2013年06月 (39件)
- 2013年05月 (42件)
- 2013年04月 (28件)
- 2013年03月 (44件)
- 2013年02月 (41件)
- 2013年01月 (48件)
- 2012年12月 (48件)
- 2012年11月 (41件)
- 2012年10月 (42件)
- 2012年09月 (44件)
- 2012年08月 (40件)
- 2012年07月 (41件)
- 2012年06月 (44件)
- 2012年05月 (44件)
- 2012年04月 (41件)
- 2012年03月 (49件)
- 2012年02月 (41件)
- 2012年01月 (43件)
- 2011年12月 (45件)
- 2011年11月 (42件)
- 2011年10月 (49件)
- 2011年09月 (44件)
- 2011年08月 (41件)
- 2011年07月 (43件)
- 2011年06月 (49件)
- 2011年05月 (44件)
- 2011年04月 (41件)
- 2011年03月 (44件)
- 2011年02月 (42件)
- 2011年01月 (44件)
- 2010年12月 (46件)
- 2010年11月 (44件)
- 2010年10月 (48件)
- 2010年09月 (44件)
- 2010年08月 (45件)
- 2010年07月 (47件)
- 2010年06月 (44件)
- 2010年05月 (46件)
- 2010年04月 (43件)
- 2010年03月 (46件)
- 2010年02月 (42件)
- 2010年01月 (42件)
- 2009年12月 (42件)
- 2009年11月 (43件)
- 2009年10月 (41件)
- 2009年09月 (43件)
- 2009年08月 (41件)
- 2009年07月 (44件)
- 2009年06月 (35件)
- 2009年05月 (41件)
- 2009年04月 (46件)
- 2009年03月 (47件)
- 2009年02月 (41件)
- 2009年01月 (43件)
- 2008年12月 (45件)
- 2008年11月 (44件)
- 2008年10月 (43件)
- 2008年09月 (42件)
- 2008年08月 (38件)
- 2008年07月 (41件)
- 2008年06月 (38件)
- 2008年05月 (42件)
- 2008年04月 (41件)
- 2008年03月 (40件)
- 2008年02月 (37件)
- 2008年01月 (42件)
- 2007年12月 (47件)
- 2007年11月 (35件)
- 2007年10月 (40件)
- 2007年09月 (34件)
- 2007年08月 (36件)
- 2007年07月 (31件)
- 2007年06月 (36件)
- 2007年05月 (41件)
- 2007年04月 (22件)
- 2007年03月 (25件)
- 2007年02月 (23件)