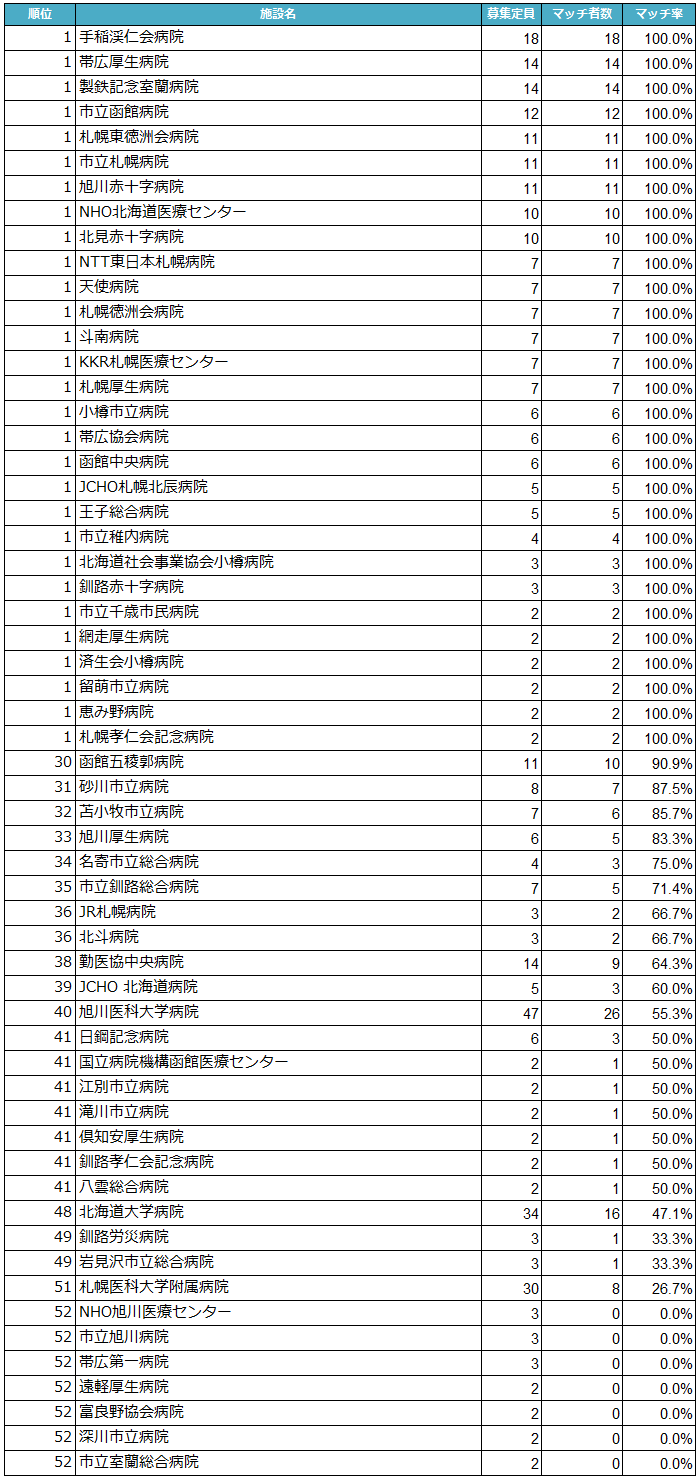厚生労働省の臓器移植委員会は5日、知的障害者などの意思表示が困難な者からの臓器提供を見合わせるとしていた従来の指針の記載を削除する方針を了承した。個別の事例に応じて慎重に判断するとの記載に改めることで、本人の意思を丁寧に推定し、尊重するのが狙い。
新たな指針の対象は15歳以上で、医療やケアに関わってきた医療従事者の助言を得ながら、主治医らが慎重に判断する。15歳未満はすでに障害の有無にかかわらず家族の同意があれば臓器提供できる。今後、意見公募を経て指針改正に向けた手続きを進める。
知的障害の程度には個人差があり、有効な意思表示ができるかどうかは個別に検討する必要がある。従来の指針は障害者からの提供を一律に見合わせるとの誤った解釈をしやすいとの指摘や、知的障害者らから「障害が理由で提供できないのは差別だ」との批判の声が上がっていた。
今年5月には日本臓器移植ネットワークが、知的障害の療育手帳を持つ人の臓器提供の意思表示を一律に無効とする運用をしていたことが発覚。厚労省は手帳を持つことのみを理由に一律に判断しないよう徹底を求める通知を出していた。