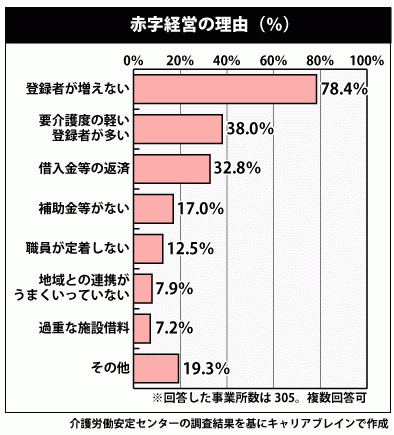社会保障と税の一体改革で厚生労働省がまとめた社会保障制度改革案が4日、明らかになった。見直しが求められている生活保護制度では、生活困窮者対策と生活保護制度の見直しを総合的に行う「生活支援戦略」(仮称)を来年秋をめどに策定することを盛り込んだ。5日に開かれる厚労省の社会保障改革推進本部で正式決定する。
年金制度では、本来より2・5%高い公的年金支給の「特例水準」を解消する措置を「来年度分から実施する」として、関連法案を2012年の通常国会に提出すると明記した。
これまで「埋蔵金」などで確保されてきた基礎年金の国庫50%負担は、一体改革で税率が引き上げられる消費税の増収分で財源を確保するとした。
医療が高額となるがん患者などの負担を軽減する「高額療養費制度」の拡充や後期高齢者医療制度の見直しなどは、12年の通常国会に向け、関係者と協議し、引き続き検討するとした。
介護職員の給与水準の維持を目的とした、健康保険組合を持つ主に大企業の従業員の介護保険料引き上げについても、12年の通常国会法案提出に向け、引き続き検討するとしている。
生活保護制度をめぐっては、受給者が205万人を超え過去最多となり、就労支援と連携した対策が求められていた。厚労省案では、生活困窮者の支援実施のために国の中期プランを策定し、生活自立支援サービスの体系化や民間非営利団体(NPO)の育成、多様な就労機会の創出などにも取り組むとしている。
共同通信社 12月5日(月) 配信