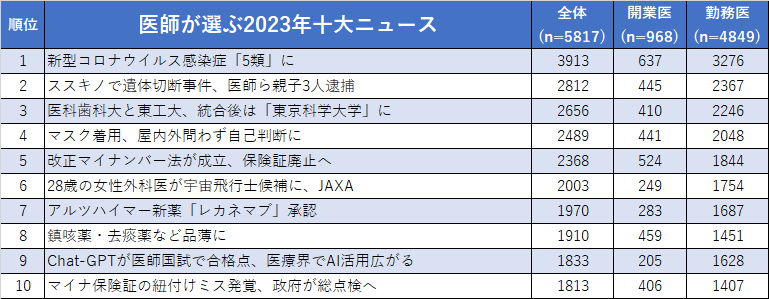厚生労働省は1月26日の中医協総会(会長:小塩隆士・一橋大学経済研究所教授)に2024年度診療報酬改定に向けた「個別改定項目について」を提示、具体的な改定内容についての議論が始まった。焦点の「賃上げ」について入院基本料、初再診料、外来診療料、調剤基本料で対応することを明示するとともに、「賃上げに向けた評価」を新設する。具体的な点数設定は今後示される(資料は厚労省のホームページ)。
2023年12月の厚労・財務相折衝で改定率のうち賃上げに用途を限定した財源が設定されており、看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種については、2024年度にベア+2.5%、2025年度にベア+2.0%と数値目標が定められている。診療側は初再診料や入院基本料での対応、支払側は条件を付けた加算などでの対応を求めていた(『医師らの賃上げ、初再診料・入院基本料の増点か加算か』)。
診療所については入院・外来医療等の調査・評価分科会で「透析や内視鏡といった初再診料による収益が多くない施設には対応が必要ではないか」との指摘があったことから追加で分析。賃金増率が1.2%に達しない医療機関を対象とした追加の評価も新設する。点数の増加分が実際に賃上げに使われているかを担保するため、計画と実績の報告も求める。
入院基本料については、施設基準で標準的な栄養評価手法の活用や、退院時も含めた定期的な栄養状態の評価を栄養管理手順に位置づけることを明確化することや、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)など適切な意思決定支援についての指針策定、身体的拘束の最小化などを要件化する。
健康保険組合連合会理事の松本真人氏は、「基本料に溶け込ませると病院と診療所の経営格差、職員配置の違いを反映できない。なぜ加算ではだめなのか」と質問。厚労省保険局医療課長の眞鍋馨氏は、若手の勤務医が大学医局人事などで短期間に勤務先が変わることや、事務職員は派遣や委託も多いことなど雇用形態が複雑であることから「広く算定されている基本料等に上乗せする対応が適切ではないかという提案だ」と回答すると、松本氏は、「最大限の実態把握と効果の検証を行い、対応が不十分な場合は見直すことを前提に了承する」と述べた。
実績報告について、診療側は日本医師会常任理事の長島公之氏が、事務的な負担、非常勤や異動のある医師も多いことから「収入と支出の総額を把握するのが限界だ」と主張。支払側は、松本氏が時間外手当は労働時間数によって変動するため、含めてしまうと賃上げによるものかどうかの判断ができなくなるとして「少なくとも基本給は(報告を)やっていただかないと実績把握は難しい」と話した。