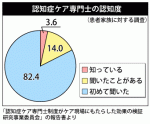厚生労働省の高齢者医療制度改革会議は12月20日、最終案を取りまとめました。75歳以上の人は、国保あるいは被用者保険に加入、国保の財政運営は二段階で都道府県単位化を進めるのが骨子(資料は、厚労省のホームページに掲載)。
細川律夫・厚生労働相は、あくまで次期通常国会に法案を提出、2013年3月からの実施を目指しています。しかし、「最終とりまとめ案」の段階に至っても、いまだ各方面からの反対があり、厚労省案通りに法案提出できるかは流動的で、先送り論も浮上しているのが現状。
20日の会議でも、国保の都道府県単位化で負担増が懸念される全国知事会は、「市町村国保の構造的問題を議論することなく、単に財政運営を都道府県に移しても巨大な赤字団体を作り、問題を先送りするだけ」などと指摘、この最終取りまとめ案に基づく新制度への移行を反対。
地方自治体の理解を得るため、厚労省は2011年1月から、「国民健康保険に関する国と地方の協議」の場を設け、厚労省の政務三役と、地方(知事・市長・町村長・広域連合長の代表)との話し合いを進める予定。
一方、与党民主党内からも、厚生労働部門会議の「高齢者医療制度改革ワーキングチーム」が、70-74歳の窓口負担を2割に引き上げる厚労省案に対し、マニフェスト通りの1割維持を主張するなど、厚労省案の見直しを迫る声が上がっています(『70-74歳は1割維持、「厚労省案で国会通るのか」』などを参照)。