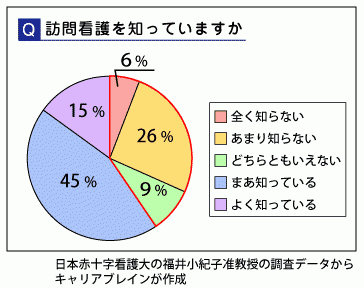39度を超える発熱が1週間続いた年男さん。誤嚥が原因ではと絶食にして数日経っても、熱は下がりません。そこでKさんは、嚥下指導のために月に2度来られている嚥下専門医に回診を頼んだそうです。
「年男さん、口を開けてください」
先生の一言に驚いたKさん。絶食しているのに、なぜ口腔内を診るのだろう?カンファレンスルームに戻ってから理由を尋ねると、先生はこういいました。
「年男さんは誤嚥性肺炎だね。誤嚥は、食べ物だけが原因じゃない。汚れただ液が肺に入ることでも起こるんだよ。だから、口腔内をキレイな状態で保つことが大事なんだ」
話を聞いて、ハッとしたKさん。
「食止め後、師長さんに確認して、毎日3回行なっていた口腔ケアを2回に減らしていたんです。それに、食べていた時に比べて目に見える汚れが減った分、ケアにかける時間も自然と短くなっていて……」
Kさんはすぐ師長さんに相談し、口腔ケアの回数を3回に戻したといいます。より丁寧にケアを行なったKさん。また、専門医のアドバイスを受け、だ液が肺に入りにくいようにベッドを30度起こして就寝してもらうことにしました。その結果、年男さんの熱は1週間程で37度5分まで低下。少しずつ体力が回復し、
ゼリー食に戻ることができたのです。
このできごとで、絶食患者さんの誤嚥リスクへの意識が変化したKさん。患者さんが食事をしているかどうかに関わらず、今まで以上に丁寧な口腔ケアを心がけているそうです。
記事一覧
誤嚥性肺炎は、食事だけが原因ではない
たんの吸引などの試行事業案を了承―厚労省検討会
厚生労働省の「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」(座長=大島伸一・独立行政法人国立長寿医療研究センター総長)は8月9日、4回目の会合を開き、前回会合で同省が提示した「たんの吸引等の試行事業案」を大筋で了承した。これに伴い、来年3月には全国約40か所の事業所で試行事業が実施される。
「たんの吸引等の試行事業案」では、事業を実施する施設として、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム、障害者(児)支援施設など(医療施設は除く)や、訪問介護事業所で「できる限り行う」と提案。また、全国約40か所の事業所で約120人の介護職員を対象に事業を実施する方針も示された。ただ、いずれの施設も、介護職員数人に対し、3年以上の実務経験を持ち、指導者講習を受講した看護師を配置するなどの条件を満たす必要があるとしている。
介護職員が手掛けられる医行為としては、「たんの吸引(口腔内と鼻腔内、気管カニューレ内部。口腔内については、咽頭の手前まで)」と「胃ろう・腸ろう・経鼻の経管栄養」としている。ただ、胃ろう・腸ろうの状態確認(1日1回)や、経鼻経管栄養のチューブ挿入状態の確認は看護職員が行うとした。
介護職員に対しては、「たんの吸引と経管栄養の両方を行う場合は、50時間の講義と、それぞれ5回以上演習」などの基本研修と、看護師の指導を受けながら所定の実習を行う実地研修が施される。なお、試行事業に参加できるのは、研修を終えた介護職員のうち、所定の評価基準を満たした職員だけと定められている。
この試行事業案に対し、ジャーナリストで国際医療福祉大大学院教授の黒岩祐治構成員は「50時間の講義は、(働いている介護職員にとって)非常なマイナス」とし、技術の有無を判定する基準を設け、その基準を満たした人材に医行為を認める制度の導入を提案した。しかし、他の多くの構成員からは「50時間の研修時間が多いか少ないか、この内容でやってみてから判断すればよい」(太田秀樹・医療法人アスムス理事長)などとする声が上がり、試行事業案は了承された。
■医行為をめぐる議論、結論持ち越し
試行事業案の了承に先立ち、たんの吸引や経管栄養を医行為から除外すべきかをめぐる議論が再燃した。三上裕司構成員(日本医師会常任理事)は「医行為の範囲の明確化をやらなければ、実際の議論はできない」と改めて主張。これに対し、「口の中だけは医行為でないとか、奥は医行為だとか、現実に線は引けない」(太田構成員)との意見のほか、「医療というものがかかわらなくなる可能性のある、誰でもできる行為になるのは全然望ましくない」(内田千恵子・日本介護福祉士会副会長)とする意見も上がり、医行為の範囲についての結論は持ち越された。
( 2010年08月09日 22:04 キャリアブレイン )
患者の暴言暴力、医師や看護師6割被害/奈良県医師会調査
奈良県医師会が医療関係者約1万7000人を対象にしたアンケートで、医師や看護師の6割が患者から暴力や暴言による被害を受けたと回答したことが分かった。医療現場でのこうした「院内暴力」は年々問題化。仕事へのやりがいをなくしたり、不安感が増すなどの悪影響もあり、医師会は行政機関と連携して対策を検討する。
奈良市では07年6月、診察中の病院長が元患者の夫にナイフで刺され、重傷を負う事件が発生。車谷典男・奈良県立医大教授らが08年9~10月、県内1020の医療機関の医師や看護師、看護補助者、事務職員を対象にアンケートを実施、約1万2000人から回答を得た(回収率約70%)。
それによると、身体、精神ともに被害を受けたことがあると回答したのは、医師61・3%▽看護師60・5%▽看護補助者37・9%▽事務職員36・7%。最も多かったのは暴言で、看護師や看護補助者は暴力が目立った。
自由記入欄には、「殴られそうになって、ステッキなどを振り回された。『おまえ雑魚や、殺したる』と電話口で言われた」▽「認知症患者にたたかれる、引っかかれる、つままれるが常態化」▽「患者の家族にストーカー行為をされた。8年がたっているが、男性患者や男性家族の前で笑顔をつくると誤解されそうで怖い」――などの回答があった。
被害を受けた医師584人のうち、32・4%が「仕事のやりがいが低下した」▽30・8%が「仕事に不安を感じた」――としており、休職したり職場を変わった例もあるという。また、被害経験者のうち、医師の9・4%、看護師の7・4%に心的外傷後ストレス障害(PTSD)とみられる症状があった。
塩見俊次・同医師会長は「医療機関に対する期待の大きさの裏返しだが、できることとできないことがある。患者を含めて考えるべき問題だ」と話している。
2010年8月4日 提供:毎日新聞社
ヘルパーと患者に温度差 たん吸引など医療行為で
通常は医師や看護師にしか認められていない、たんの吸引などの医療行為について、国はホームヘルパーや介護福祉士にも容認するかどうか、検討を進めている。
在宅患者は、ケアに追われる家族の負担軽減につながると早期実施を主張。一方、ヘルパーらは「本当に安全を確保できるのか」と慎重な構えで、温度差が浮き彫りになっている。
▽公然の秘密
議論の的となっているのは、たんの吸引と、口からの食事ができない人の胃に管で流動食を流し込む「胃ろう」。処置を誤ると事故につながりかねず、医師法で医療従事者に限定されている。
だが、さまざまな介護を必要とする高齢者が多い特別養護老人ホームでは、看護師がいない夜間に介護職員がやむを得ず対応するケースが多く、違法状態は「公然の秘密」だった。
特養で何度も吸引をした関東地方に住む介護福祉士の女性は「夜中にいちいち看護師を呼ぶ余裕はない。誰もが仕方ないと黙認している」と、苦しい事情を打ち明ける。
このため厚労省は、鼻や気管より危険性が低い口からの吸引などについて「書面による同意」など一定の条件で特養の介護職員も可能とした。さらに有識者の検討会を設け、有料老人ホームなどの介護職員やヘルパーも容認する対象に加えるかどうか、議論を始めている。
厚労省は将来、施設介護での医療提供に力を入れるよりも、要介護者が在宅で24時間、いつでもケアを受けられる訪問サービスを推進したい考え。高齢者宅を訪れるヘルパーに吸引などを認める環境を早期に整えたいとしている。
▽早期実現への課題
厚労省は、今夏をめどに中間取りまとめを行い、モデル事業を実施したい考えだが、さまざまな課題が浮かび上がっている。
過去にもヘルパーに吸引のみを認めたことがあるが、例外扱いとされ、現場は安全面で不安をぬぐえず結果的に普及しなかった。このため、ヘルパーの間では「介護職員も医療行為ができると明記してほしい」と求める声が強い。
「技術習得向けの研修を受けられる環境が整わないと、現場の不安は解消されない」(全国ホームヘルパー協議会)とする意見もある。
吸引を認める職員の範囲も問題だ。技術の有無を資格で認定しようという意見もあるが、難病の筋萎縮(いしゅく)性側索硬化症(ALS)の在宅患者で、検討会メンバーの橋本操(はしもと・みさお)さんは「急に資格が必要となっても、資格を持っていないヘルパーたちが急に取れるかどうか分からない。常に吸引を必要とする人にとっては死活問題だ」と指摘する。
ヘルパーと介護福祉士にたんの吸引など認める方針―厚労省検討会
厚生労働省の「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」(座長=大島伸一・独立行政法人国立長寿医療研究センター総長)は7月22日、2回目の会合を開き、ホームヘルパーと介護福祉士に対し、たんの吸引と胃ろうによる経管栄養の実施を認める方針で合意した。次回以降の会合で、具体的な研修内容などを検討する。
会合では、日本看護協会常任理事の齋藤訓子氏が、▽急性期やターミナル期における医行為は、医師もしくは指示を受けた看護職員が行う▽経管栄養については、現行の特別養護老人ホームにおける対象範囲・実施体制を踏襲すべき。経鼻経管栄養については、介護職員の実施は認めるべきではない▽老人保健施設におけるたんの吸引や経管栄養については、医師もしくは看護職員が実施すべき―などの内容を盛り込んだ意見書を大島座長あてに提出した。
これに対し、ジャーナリストで国際医療福祉大大学院教授の黒岩祐治氏は、「ならば、すべてのナースは(たんの吸引などの医行為を)ちゃんとできるのか、と問いたい。看護師ならできる、介護士はできないという発想は間違い」と激しく反論した上で、法律上、介護職員がたんの吸引などの医行為ができないと定められている現状こそが危険と主張。他の構成員も、ホームヘルパーと介護福祉士に対し、たんの吸引と経管栄養を認めることを前提に、研修や法整備についての議論を進める方針に賛同した。
さらに日本医師会常任理事の三上裕司氏は、医行為を行うことができないはずの介護職員が、たんの吸引や経管栄養を実施するという矛盾を解消するため、「(たんの吸引などは)医行為から外すことが現実的ではないか」と提言した。しかし、国学院大法科大学院長の平林勝政氏は、「介護職が医行為をできるようにするためには、どこでどんな教育をしていくのか、という議論をまず進めるべき。その上で(医行為かどうかという)法律に関する議論をすべきではないか」と主張。多くの構成員が、法整備より研修の内容の検討を優先することで一致した。
自己負担無料化廃止へ「不公平感招く」/16国保組合
医療費の自己負担を無料化している16の国保組合が23年度以降、無料化を廃止する方針であることが5月31日、厚労省の調べで分かった。給付費に対し平均4割の国庫負担が投入されている国保組合が自己負担を無料化するのは「国民の疑念や不公平感を招きかねない」と厚労省が判断、是正を促していた。結核・精神障害の医療費の自己負担を無料化している国保組合も無料化を廃止する方針。
財政力のある国保組合 補助見直しへ/23年度から
厚労省は加入者の所得が高い国保組合に対する国庫補助を23年度予算から見直す方向で検討に入った。5年ぶりに実施した国保組合の所得調査結果を踏まえ、具体的な見直しとなる対象組合や見直し額を決める。
厚労省が昨年実施した所得調査の速報値によると、医師国保の所得(市町村民税課税標準)が676万円と突出して高かった。所得が高い国保組合は財政調整補助金を全く交付されていないケースもあることから、32%の定率補助の見直しに着手する可能性もある。
この場合、国保法の改正が必要となる。同省は併せて財政調整補助金や国保特別対策費補助金の配分方法・補助内容も見直す構えで、国保組合の補助体形の抜本改革を図りたい考えだ。
「訪問看護知らない」が3割強
「訪問看護を知らない」とする人が3割強に達するなど、訪問看護サービスの周知が低いことが、7月15日までに日本赤十字看護大の福井小紀子准教授ら研究班の調査で分かった。
【関連記事】
24時間訪問看護の調査研究開始へ―全訪看
訪問看護ステーション、微減の5731件
24時間訪問介護の検討会が初会合―厚労省
地域ケア研究会報告、「施設解体」と懸念―全国老施協・中田会長
夜間対応型訪問介護、認知度アップや人材確保が課題
研究班による「在宅終末期医療の望ましいあり方に関する調査」は、2000人を対象にアンケート形式で実施。約1000人から回答を得た。
訪問看護サービスの存在について、「全く知らない」は6%、「あまり知らない」は26%だった。「どちらともいえない」を含めた訪問看護サービスの存在を正しく認識していない人は4割に達した。また、終末期に保険を使って訪問看護が利用できることについては、「全く知らない」「あまり知らない」と回答したのは62%だった。
福井准教授は、「訪問看護は国民への周知が不十分。終末期の訪問看護利用が可能なことを周知することで、在宅終末期医療や在宅看取りが進む可能性が示された」としている。
訪問看護の自己負担額については、「入院中にかかる医療費と比べて自宅療養の自己負担額はどの程度が適当か」との質問に対し、「入院中よりはるかに安い」が28%、「入院中の半額程度」が26%だった。これについて福井准教授は、「5割以上の国民が入院中に比べて半額以下が妥当と考えていたことが分かった」としている。
( 2010年07月15日 17:11 キャリアブレイン )
過去ログ
- 2026年02月 (18件)
- 2026年01月 (31件)
- 2025年12月 (26件)
- 2025年11月 (24件)
- 2025年10月 (26件)
- 2025年09月 (20件)
- 2025年08月 (22件)
- 2025年07月 (21件)
- 2025年06月 (12件)
- 2025年05月 (13件)
- 2025年04月 (5件)
- 2025年03月 (11件)
- 2025年02月 (11件)
- 2025年01月 (13件)
- 2024年12月 (22件)
- 2024年11月 (22件)
- 2024年10月 (20件)
- 2024年09月 (17件)
- 2024年08月 (24件)
- 2024年07月 (16件)
- 2024年06月 (13件)
- 2024年05月 (23件)
- 2024年04月 (17件)
- 2024年03月 (13件)
- 2024年02月 (19件)
- 2024年01月 (16件)
- 2023年12月 (27件)
- 2023年11月 (17件)
- 2023年10月 (14件)
- 2023年09月 (17件)
- 2023年08月 (17件)
- 2023年07月 (16件)
- 2023年06月 (18件)
- 2023年05月 (14件)
- 2023年04月 (16件)
- 2023年03月 (20件)
- 2023年02月 (14件)
- 2023年01月 (12件)
- 2022年12月 (21件)
- 2022年11月 (16件)
- 2022年10月 (17件)
- 2022年09月 (17件)
- 2022年08月 (16件)
- 2022年07月 (15件)
- 2022年06月 (20件)
- 2022年05月 (10件)
- 2022年04月 (14件)
- 2022年03月 (22件)
- 2022年02月 (15件)
- 2022年01月 (17件)
- 2021年12月 (18件)
- 2021年11月 (13件)
- 2021年10月 (24件)
- 2021年09月 (16件)
- 2021年08月 (17件)
- 2021年07月 (20件)
- 2021年06月 (14件)
- 2021年05月 (15件)
- 2021年04月 (20件)
- 2021年03月 (22件)
- 2021年02月 (10件)
- 2021年01月 (10件)
- 2020年12月 (15件)
- 2020年11月 (15件)
- 2020年10月 (16件)
- 2020年09月 (15件)
- 2020年08月 (19件)
- 2020年07月 (15件)
- 2020年06月 (14件)
- 2020年05月 (19件)
- 2020年04月 (12件)
- 2020年03月 (9件)
- 2020年02月 (18件)
- 2020年01月 (14件)
- 2019年12月 (23件)
- 2019年11月 (11件)
- 2019年10月 (15件)
- 2019年09月 (20件)
- 2019年08月 (12件)
- 2019年07月 (19件)
- 2019年06月 (19件)
- 2019年05月 (14件)
- 2019年04月 (11件)
- 2019年03月 (14件)
- 2019年02月 (10件)
- 2019年01月 (5件)
- 2018年12月 (16件)
- 2018年11月 (15件)
- 2018年10月 (15件)
- 2018年09月 (16件)
- 2018年08月 (6件)
- 2018年07月 (32件)
- 2018年06月 (17件)
- 2018年05月 (11件)
- 2018年04月 (24件)
- 2018年03月 (14件)
- 2018年02月 (8件)
- 2018年01月 (17件)
- 2017年12月 (15件)
- 2017年11月 (26件)
- 2017年10月 (22件)
- 2017年09月 (30件)
- 2017年08月 (24件)
- 2017年07月 (14件)
- 2017年06月 (27件)
- 2017年05月 (10件)
- 2017年04月 (23件)
- 2017年03月 (21件)
- 2017年02月 (14件)
- 2017年01月 (31件)
- 2016年12月 (25件)
- 2016年11月 (18件)
- 2016年10月 (17件)
- 2016年09月 (15件)
- 2016年08月 (9件)
- 2016年07月 (10件)
- 2016年06月 (19件)
- 2016年05月 (10件)
- 2016年04月 (13件)
- 2016年03月 (13件)
- 2016年02月 (14件)
- 2016年01月 (15件)
- 2015年12月 (26件)
- 2015年11月 (31件)
- 2015年10月 (31件)
- 2015年09月 (37件)
- 2015年08月 (40件)
- 2015年07月 (37件)
- 2015年06月 (40件)
- 2015年05月 (33件)
- 2015年04月 (33件)
- 2015年03月 (29件)
- 2015年02月 (32件)
- 2015年01月 (27件)
- 2014年12月 (29件)
- 2014年11月 (27件)
- 2014年10月 (31件)
- 2014年09月 (34件)
- 2014年08月 (34件)
- 2014年07月 (35件)
- 2014年06月 (48件)
- 2014年05月 (42件)
- 2014年04月 (38件)
- 2014年03月 (43件)
- 2014年02月 (38件)
- 2014年01月 (37件)
- 2013年12月 (43件)
- 2013年11月 (41件)
- 2013年10月 (44件)
- 2013年09月 (44件)
- 2013年08月 (41件)
- 2013年07月 (33件)
- 2013年06月 (39件)
- 2013年05月 (42件)
- 2013年04月 (28件)
- 2013年03月 (44件)
- 2013年02月 (41件)
- 2013年01月 (48件)
- 2012年12月 (48件)
- 2012年11月 (41件)
- 2012年10月 (42件)
- 2012年09月 (44件)
- 2012年08月 (40件)
- 2012年07月 (41件)
- 2012年06月 (44件)
- 2012年05月 (44件)
- 2012年04月 (41件)
- 2012年03月 (49件)
- 2012年02月 (41件)
- 2012年01月 (43件)
- 2011年12月 (45件)
- 2011年11月 (42件)
- 2011年10月 (49件)
- 2011年09月 (44件)
- 2011年08月 (41件)
- 2011年07月 (43件)
- 2011年06月 (49件)
- 2011年05月 (44件)
- 2011年04月 (41件)
- 2011年03月 (44件)
- 2011年02月 (42件)
- 2011年01月 (44件)
- 2010年12月 (46件)
- 2010年11月 (44件)
- 2010年10月 (48件)
- 2010年09月 (44件)
- 2010年08月 (45件)
- 2010年07月 (47件)
- 2010年06月 (44件)
- 2010年05月 (46件)
- 2010年04月 (43件)
- 2010年03月 (46件)
- 2010年02月 (42件)
- 2010年01月 (42件)
- 2009年12月 (42件)
- 2009年11月 (43件)
- 2009年10月 (41件)
- 2009年09月 (43件)
- 2009年08月 (41件)
- 2009年07月 (44件)
- 2009年06月 (35件)
- 2009年05月 (41件)
- 2009年04月 (46件)
- 2009年03月 (47件)
- 2009年02月 (41件)
- 2009年01月 (43件)
- 2008年12月 (45件)
- 2008年11月 (44件)
- 2008年10月 (43件)
- 2008年09月 (42件)
- 2008年08月 (38件)
- 2008年07月 (41件)
- 2008年06月 (38件)
- 2008年05月 (42件)
- 2008年04月 (41件)
- 2008年03月 (40件)
- 2008年02月 (37件)
- 2008年01月 (42件)
- 2007年12月 (47件)
- 2007年11月 (35件)
- 2007年10月 (40件)
- 2007年09月 (34件)
- 2007年08月 (36件)
- 2007年07月 (31件)
- 2007年06月 (36件)
- 2007年05月 (41件)
- 2007年04月 (22件)
- 2007年03月 (25件)
- 2007年02月 (23件)