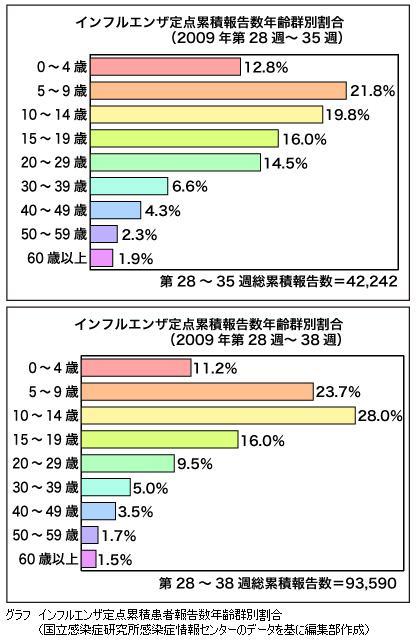世界的に、特に若い世代において、噛みタバコ、嗅ぎタバコといった無煙タバコ製品の使用が増えている。フランス癌研究所のPaolo Boffetta氏らは、メタ分析を行い、無煙タバコの使用が心筋梗塞死亡と脳卒中死亡のリスクを有意に高めることを明らかにした。詳細は、BMJ誌2009年8月29日号に報告された。
無煙タバコが人に対する発癌性を持つことは明らかだが、それ以外にも、心筋梗塞、脳卒中、不妊などに対する影響が懸念されている。罹患率と死亡率が高い心血管疾患との関わりを明らかにすることが重要と考えた著者らは、観察研究の系統的レビューとメタ分析を行った。
PubMed、ISI Web of Scienceに登録された研究の中から、無煙タバコ製品の使用と心筋梗塞、脳卒中リスクの関係を定量的に推定した研究を探した。アジアで流通している無煙タバコは、欧州や北米で市販されている製品とは異なるため、アジアで行われた研究は除外した。
スウェーデンで行われた8件と米国で行われた3件、計11件の研究(論文は10本)を選出。対象者は主に男性だった。8件は前向きコホート研究、3件は集団ベースのケースコントロール研究で、9件は喫煙歴のない人々のみを対象にしており、2件は過去に喫煙歴がある人も含めていた。
ランダム効果モデルを用いてサマリー相対リスクを求めた。
あらゆる心筋梗塞のリスクについて分析していたのは、9件の研究。無煙タバコ製品の使用歴と心筋梗塞リスクの間に有意な関係は見られなかった(使用歴なし群と比較した相対リスクは0.99、95%信頼区間0.89-1.10)。無煙タバコの現在の使用者に限定しても、相対リスクは1.03(0.91-1.17)で有意差なし。
致死的心筋梗塞について分析していたのは8件の研究。無煙タバコ製品の使用歴がある人々の相対リスクは1.13(1.06-1.21)と有意で、リスク上昇は現在の使用者のみに見られた(1.17、1.09-1.25)。過去の使用者では0.76(0.58-0.99)だった。
あらゆる脳卒中について分析していたのは、6件の研究。無煙タバコ使用歴あり群のリスクは1.19(0.97-1.47)で、差は有意ではなかった。
致死的脳卒中について分析していたのは5件。無煙タバコ使用歴あり群の相対リスクは1.40(1.28-1.54)と有意に高く、現在の使用者は1.44(1.31-1.59)、過去の使用者は0.86(0.26-2.79)となった。
スウェーデンで行われた研究と米国で行われた研究を別個に分析しても、致死的な心筋梗塞と脳卒中による死亡リスクには有意な上昇が見られた。
心筋梗塞または脳卒中による死亡と、無煙タバコ製品の使用頻度または使用期間の関係についてのデータは限定的にしか得られず、強力な用量反応関係は見出せなかった。
人口寄与割合を推定したところ、無煙タバコの使用は米国の心筋梗塞死亡の0.5%、スウェーデンでは5.6%に寄与しており、脳卒中死亡におけるその割合はそれぞれ1.7%と5.4%になった。
以上のように、無煙タバコ製品の使用と致死的心筋梗塞、致死的脳卒中リスクの関係が示唆されたが、リスク上昇幅はさほど大きくなかった。今後さらに研究を進めて、無煙タバコ製品の作用機序を明らかにする必要がある、と著者らは述べている。