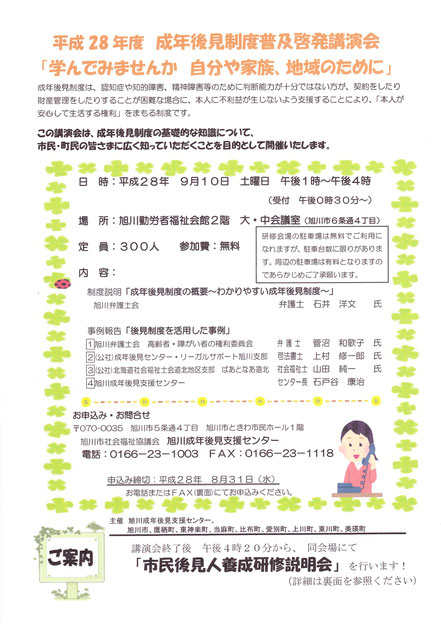国民健康保険を運営する市町村が、診療報酬明細書(レセプト)などの情報を活用し、医療費の抑制や住民の健康づくりに役立てている。保健師らが、住民の通院歴や健診の結果を分析し、生活習慣の改善を指導するほか、医療機関の受診を促して重症化を予防する。広島県呉市の取り組みが全国に広がり、道内でも岩見沢市や函館市など100を超す市町村が着手している。
■生活習慣病の予防も
「血糖値が正常になった。体調もいい」。糖尿病を患う岩見沢市の大島英敏さん(74)は昨年、市の「重症化予防プログラム」に参加した効果を実感する。
14年前に糖尿病と診断され薬を飲み始めたが、生活習慣は変えなかった。昨夏、市の保健師からプログラム参加を促された。「糖尿病が進行すると、腎臓機能が低下し人工透析が必要になると言われ、困惑しました」。半年間の改善指導を受け、禁酒や運動に取り組んだ。終了時には体重が8キロ減の66キロになった。
市は国保加入者約30万件のレセプトから病状や薬の種類、通院歴を分析。糖尿病が悪化する危険の高い人を昨年度までの2年間で計542人選び、プログラム参加を打診した。うち49人が応じ、多額の費用がかかる人工透析を全員回避できているという。
レセプトや、メタボリック症候群を予防する特定健診の結果を健康づくりや医療費の削減に生かす取り組みは「データヘルス」と呼ばれる。レセプトなど医療データの電子化が普及したことで可能となった。
岩見沢市は2014年度に着手した。重症化予防プログラムのほか、健診で異常が見つかったのに放置する人に受診を勧めたり、安価なジェネリック医薬品(後発薬)への切り替えを促したりする対策を行った。市は国保会計の累積赤字が3億円に達している。市国保医療助成課の背戸田巧主査は「医療費抑制は大きな課題。人工透析を受ける人が減れば意味がある」と話す。
岩見沢市が参考にしたのが、10年度にデータヘルスを全国の自治体で初めて導入し、成果を上げる呉市。政府も13年に閣議決定した「日本再興戦略」で、国保を運営する市町村などにデータヘルス計画を14年度以降に作成するよう求めた。
道の調査によると、15年10月末時点で道内の国保では53保険者(自治体)が計画を策定済み。63保険者が15年度中に策定予定と回答した。函館市は15年度に策定。後発薬の利用を促した分だけでも年間4千万~5千万円の歳出削減効果があるという。石狩市も16年度から重症化予防を実施、札幌市は16年度中の計画策定を目指す。
道内先駆けの岩見沢市では課題も浮上。重症化予防プログラムの参加を昨年促された患者は「なぜ自分が選ばれたか分からず不気味」と感じて参加を断ったという。
データの扱いについて、厚生労働省は「レセプトなどの情報は保険者が管理しており、広報などで被保険者(住民)に事前周知すれば、活用するのは問題ない」とする。ただ、東北大大学院の辻一郎教授(公衆衛生学)は「保険者は事業の趣旨や効果などを丁寧に説明し、理解してもらう努力が必要」と助言する。