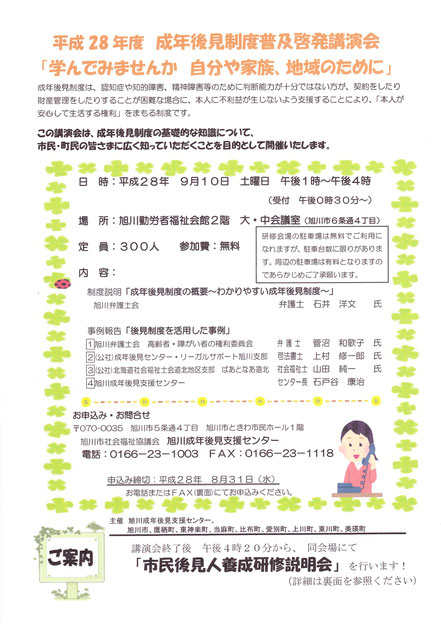19人もの障害者が未明に襲われ命を奪われた。しかも、そこを退職した職員によって。陰惨だ。もう二度と起きてほしくない。
容疑者は衆院議長に宛てた手紙の文面で「障害者が安楽死できる世界」を求めていたという。ドキッとした。というのも、私も筋萎縮性側索硬化症(ALS)の母の安楽死を真剣に望んでいた時期があったから。24時間の介護労働に加えて、意思疎通が難しくなり、閉塞(へいそく)感がピークに達していた時だった。
この事件が起きた直後に、NPO活動で同僚のALS当事者に聞いてみた。発症から30年、呼吸器を付けて生きてきた橋本操は、わずかに動く口の形をヘルパーに読み取らせて「(死刑にならないように)嘆願書を」と。また5月の衆院厚生労働委員会に参考人として招かれながら「コミュニケーションに時間がかかる」という理由で、意見陳述の機会を奪われた岡部宏生は「社会の構造の問題」と言った。
言葉を自由に操れない障害者は例外なく、あらゆる場面で非人道的な扱われ方をされている。だから、この日本社会は、この事件の容疑者と大して違わない思いを抱いている人だらけで、この男だけを責めても何も解決しないということだ。
事件発生から1週間がたったが、事件の全容が見えない。襲われた津久井やまゆり園の関係者や遺族の気持ちを思うといたたまれずつらくなるが、障害者たちが施設の中でどのように共同生活していたかが知りたい。いくつかの障害を併せ持つ「重複障害」の人を殺りくしたというが、重複にもいろいろある。一人一人の障害がどうであったのか、どんなコミュニケーション手段を取っていたか、私は知りたい。
だが、被害者の情報提供がタブーになっている。個人名も明かされないという事情。収容施設の対応である。社会や家族から隔離された重度障害者の状況が、社会からドロップアウトして、ここに逃げ込んできたこの男の心の闇を増幅したのではないか。
私も一時期、冒頭で述べたように、意思疎通ができない人の生存が無意味に思えて仕方なかった。だが、重度障害があっても地域で介護を受けて自由に伸び伸び暮らしている人たちと知り合い、疲れて傷んだ心が癒やされ考え方が一変した。一緒に街に出かけたり、宴会をしたりという、普通の暮らしを共にする中で、彼らの個別固有の障害に対して、的確な介護で応えたい気持ちがむくむくと湧いてきた。そして、意思疎通が難しい人の気持ちを必死で読み取るようになっていた。他者との共生の楽しさに目覚めた。
この事件はまれに見る凶悪犯罪で許しがたいが、重度障害者や認知症高齢者になるくらいなら、死んだほうがましというのは、よく聞く話だ。でも、重度障害者から見れば、その本質は容疑者の思想とそう変わらない、共生を否定した差別である。自分の心の闇にも目を凝らしてみたい。