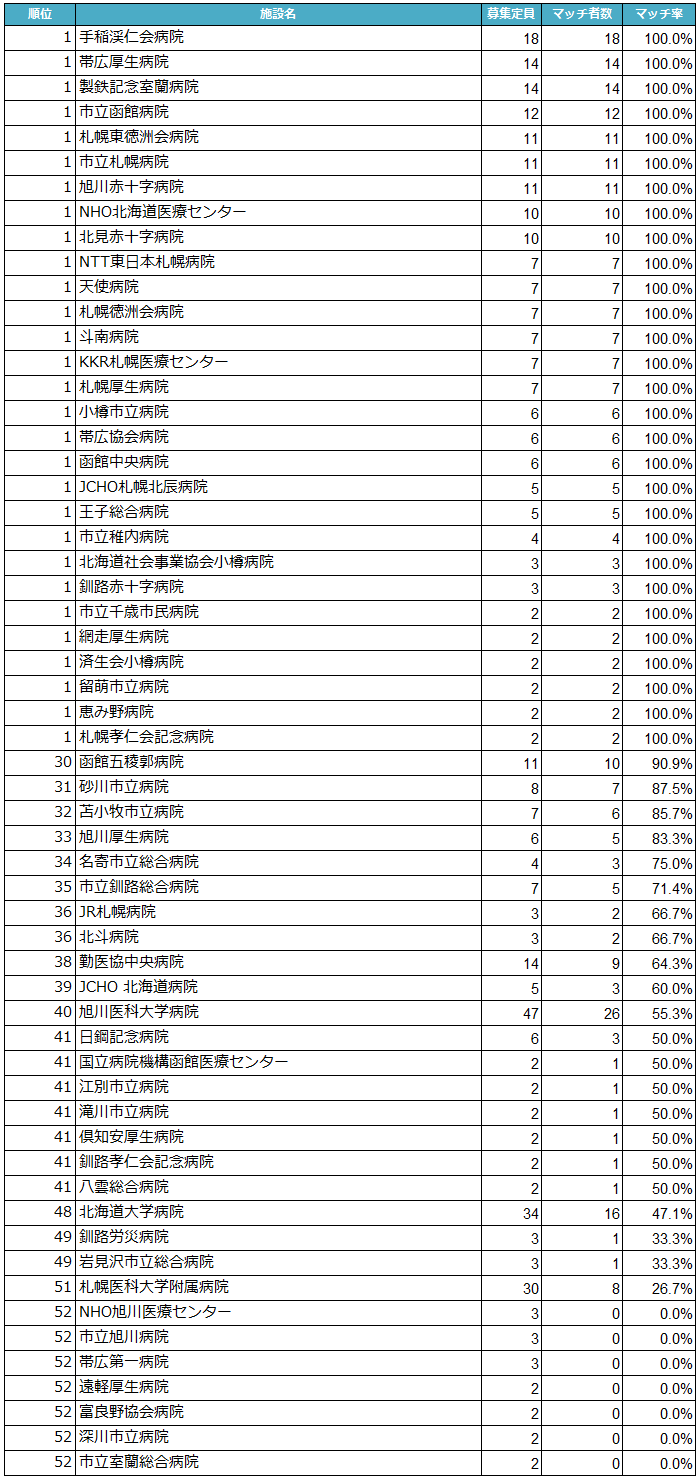こども家庭庁は来年度から、発達障害の可能性を見極めるのに有効な「5歳児健診」の普及に乗り出す。早期に障害がある子どもを支援し、症状の改善につなげるのが狙い。健診に必要な医師らを確保する費用や研修費を自治体に補助し、14%にとどまる実施率を2028年度までに100%にすることを目指す。
母子保健法は、1歳半と3歳児の健診を自治体に義務付けているが、5歳児健診は任意となっており、22年度の実施率は14・1%。多くの子どもは3歳児健診後、小学校入学前に受ける「就学時健診」まで、約3年の空白期間がある。
文部科学省によると、22年度に自閉症などの発達障害があって特別支援学級に通う児童は、約13万人に上った。就学時健診を機に発達障害が判明しても、進路選びや学校側の支援体制の構築に時間が足りないという課題があった。
5歳になると社会性が高まり、発達障害が認知されやすくなる。5歳児健診を実施している大分県竹田市で行われた研究では、自己表現や集団行動が苦手だった発達障害の子どもの多くが、支援を受けた結果、通常学級で過ごした。
全国的な普及に向け、こども家庭庁が健診を行っていない自治体に聞き取りをしたところ、「医師が確保できない」「発達障害児の支援体制の整備が難しい」といった声が寄せられた。
このため、同庁は来年度から医師の派遣に必要な費用のほか、発達障害児をサポートする保健師、心理士向けの研修費を補助する。5歳児健診を行う自治体への補助額についても、1人あたり3000円から5000円に引き上げる。
自治体には発達障害と判明した場合、子どもが在籍する保育所などで個別の支援計画を作るよう要請。円滑な学習や集団生活につなげるため、入学先の小学校にも伝えるよう求める。総務省の人口推計では、23年10月1日現在の5歳児は約91万5000人だった。