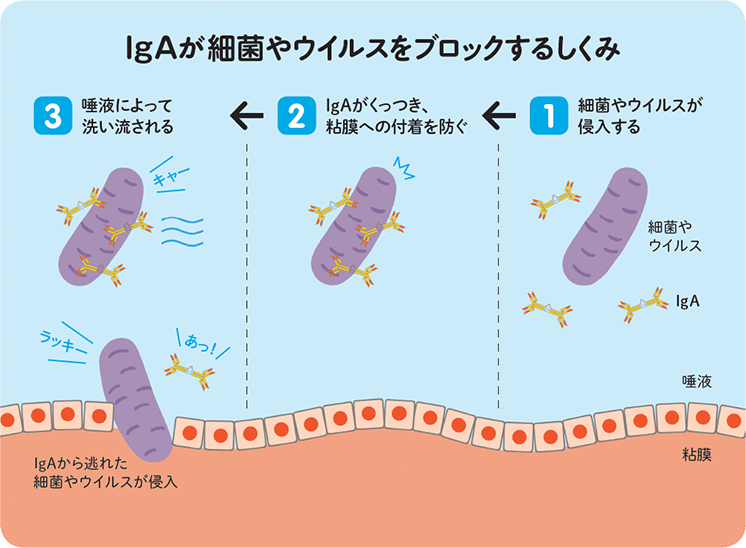近年、n-3系とn-9系の油を上手に摂れる地中海食が注目されています。地中海食はイタリア、ギリシャ、スペインなどの地中海沿岸の国の人が食べている伝統的な料理のことで、肥満を予防・改善するダイエット関連のワードとして目にすることも多くなりました。地中海食の定義は広く、特徴としては加工度を最小限にとどめ、その地域でとれた旬の新鮮な食材を使った料理であること。
魚介類やオリーブオイル、ナッツ類などを多用し、赤身肉の使用と加糖(菓子)を減らして、植物性食品が豊富に摂れるような食事のパターンになっています。
地中海食は死亡率の低下や、心血管疾患、がん、アルツハイマー病などの発生率の低下との関連が多数報告されています。複雑な調理手順がなく、入手の難しい食材や特別な調理器具も必要としないので、日常の食事に気軽に取り入れてみてはどうでしょうか。
記事一覧
地中海食で健康増進を
唾液で迅速に大腸がん検査 慶応大、短時間で高精度に
慶応大先端生命科学研究所(山形県鶴岡市)の曽我朋義(そが・ともよし)教授らは3日までに、唾液による大腸がん検査について、多くの人から採取した検体を一度に測定する技術を開発したと発表した。精度も高い上、検査に要する時間が大幅に減り、手軽ながん診断へ期待がかかる。成果は国際的な分析化学誌電子版に掲載された。
大腸がんなどの患者の唾液や尿からは、一般の人に比べ高濃度のポリアミンと呼ばれる成分が検出される。鶴岡市のベンチャー企業「サリバテック」が専用の検査キットを開発するなど、唾液中のポリアミン濃度からがんのリスクや有無を調べる方法は近年普及が進んでいる。
従来は1検体ずつ10分以上かけて調べたが、新たな技術では40検体をまとめて40分で測定できる。1検体当たり1分で終了する計算だ。また大腸がん患者と健常者から採取したポリアミンを調べたところ、8割以上の精度で両者を区別できた。一般的な便潜血検査に比べ手間がかからず、精度も高いという。
他に膵臓(すいぞう)がん、乳がん、口腔(こうくう)がんでも唾液中のポリアミン濃度が上昇することが分かっており、これらの検査にも応用できる可能性がある。
今後、サリバテックへ技術を導入し、実用化と大幅なコスト削減を目指す。曽我教授は「安く検査できればがんの早期発見にもつながる」と期待する。
注)分析化学誌は「ジャーナル・オブ・クロマトグラフィーA」
宇宙旅行時代の到来
米国で宇宙旅行サービスの実現を目指す動きが相次いでいます。
英起業家のリチャード・ブランソン氏が7月11日、自身で創業した米ヴァー
ジン・ギャラクティックの機体で宇宙空間に到達。米アマゾン・ドット・コム
創業者のジェフ・ベゾス氏も2000年に設立した米ブルーオリジンの宇宙船での
宇宙飛行に成功しました。価格は1人2000万円台が想定され、宇宙に行くのが
「夢」ではない時代が訪れようとしています。
ヴァージンが提供する宇宙旅行の価格は25万ドル(約2800万円)を計画し、
2022年の運航開始を目指しています。上空で母船から切り離した宇宙船が
ロケットエンジンで宇宙へ向かい、地上と宇宙の「境界」とされる高度100キロ
メートル付近に到達後、即座に地上に戻ってくる飛行方式です。世界で約600人
が予約していますが、今は受け付けを中断している状況です。
ヴァージンが翼を備える飛行機のような宇宙船を使うのに対し、ブルーオリ
ジンは垂直に離陸するロケットからカプセルを切り離して宇宙に向かいます。
ヴァージンが11日に到達したのは高度約86キロメートル。それに対して「100
キロメートルまで到達できる」「飛行機サイズの窓ではなく、107センチメー
トル×71センチメートルの大きな窓を備えている」と優位性を強調しています。
価格は未定ですが、20万~30万ドル(約2200万~3300万円)になると推定され
ています。
ベゾス氏やブランソン氏が目指す高度100キロメートルへの宇宙の旅は、従
来の高度400キロメートルの国際宇宙ステーション(ISS)への滞在費用が数十
億円とされるのに比べると、格段に行きやすい価格設定になっています。
2021年は「宇宙旅行元年」になる可能性がありますが、その先には月面など
のより遠い領域を巡るビジネスの戦いや、さらには宇宙機を都市間の高速移動
に応用する構想もあります。
米テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)率いるスペースXは今秋
に高度540キロメートルへの宇宙旅行、2023年には地球から約38万キロメート
ル離れた月を周回する旅行を計画しています。月を周回する旅程は5日23時間
で、ヴァージンやブルーオリジンの高度100キロメートルよりも本格的な旅行
です。また、世界中のあらゆる場所を1時間以内で移動できるようにする(ロ
ンドン→ニューヨーク:29分、ニューヨーク→パリ:30分等)との計画も掲げ
ています。
宇宙空間の移動は、リスクを伴うと共に、巨大な市場を生み出す可能性を秘
めています。起業家による宇宙を巡る戦いは、今後さらに激しくなりそうです。
歯科医師によるワクチン接種
延べ3,813人の歯科医師が5・6月に、延べ23万2,940人に対してワクチン接種を行なっている。日本歯科医師会の15日の定例記者会見で堀 会長と柳川副会長が報告したもので、47都道府県歯科医師会のうち、26歯科医師会が接種を行なっている現状を明かした。
堀 会長は、Eシステムを活用したワクチン接種の事前研修の受講者が13日時点で1万8,045人と説明し、「予想をはるかに超えた数で、全国の歯科医師の強い使命感の発露と受け止め、感謝申し上げる」と述べた。さらにワクチン接種に携わった数などについて報告した総理、官房長官、厚労大臣などから感謝の言葉があったと紹介した。
柳川副会長は、Eシステムを使った事前研修の受講者のうち、約6,800人が初めてEシステムを使った人とわかったと言及。ITが苦手などの理由でEシステムを使ってこなかった会員もいるとの認識を示し、「国難にあってワクチン接種が必要だと使命感に燃えて受けたことを強く感じた」と強調した。
【歯科通信】
歯科手術の遠隔支援検証へ「5G」「XR」「3D模型」を活用
「5G(第5世代移動通信システム)ネットワーク」と、現実世界と仮想世界を融合させる「XR」、「3Dプリンティング技術」を使い、遠隔からの歯科手術支援の有効性を検証する実証実験プログラムが7月12日から始まった。歯科医師の宇野澤元春 氏が代表を務めるDental Prediction(東京都北区)と医療用VRなどを手掛けるHoloeyes社(東京都港区、谷口直嗣 社長)とソフトバンク(東京都港区、宮川潤一 社長)が協力して行うもので、最終的には、東京の指導医が遠隔支援をしながら、若手歯科医師が大阪市内の歯科クリニックで実際の患者の手術を行い、安全性と確実性を検証する。
【日本歯科新聞】
口腔ケアで免疫力アップ!
人の免疫は、害を与える微生物などに対して働き、病気を軽く済ませてくれたり、発症を未然に防いでくれたりします。この病気の発症は、微生物の悪さをする力と免疫力のバランスが崩れた時に生じるのです。このバランスを免疫力優位にしておく必要があります。その方法の1つが、口腔ケアです。口の中には、細菌が沢山いるのをご存知ですか? 常在細菌といって、体を守る働きを示すものもありますが、悪さをする細菌もいます。この悪さをする細菌やウイルスを減らすことが大切です。細菌の塊であるプラークは、歯磨きをしないと落とすことはできません。口の中には、もう1つ細菌の塊があります。それは舌の表面についた舌苔です。これらの細菌を口腔ケアにより減らすことで、口腔の免疫が十分に働くことができるようになるのです。口腔の免疫は、IgA(※)という抗体が働き、害を及ぼす微生物を排除してくれる粘膜免疫というシステムで実行されています。しかし、このIgAも口の中が汚れていれば、敵が多すぎて、防衛が難しくなってしまうのです。
医科と連携して口腔ケア 大分県歯科医師会長の脇田晴彦氏に聞く
6月の総会で、大分県歯科医師会長に脇田晴彦氏(佐伯市)が就任した。食事や会話を楽しむ他、かみ合わせを調整することでバランス感覚が良くなり高齢者の歩行を改善することにもつながるとされ、口の健康は健康な生活を送るのに欠かせない。新型コロナウイルス禍による診療への影響や口腔(こうくう)ケアを通じた地域社会への貢献などを聞いた。
―コロナ禍での新体制の発足となった。どのように運営をしていくか。
新型コロナ感染拡大の影響を受け、この1年半は、実際に集まって開く研修会や交流などが全くできなかった。実際に集まって情報交換をしたり、手技を学ぶことは大切だと改めて実感している。ただ、インターネットでの研修で最新の話題などは共有しているので、コロナ禍でも会員がスキルアップができるようにしっかり支援したい。
―診療への影響は。
治療よりも定期検査を控える人が増えているようだ。口は食べる、話すなどの機能を担い、生活の質(QOL)を支える場所なので、日常的な口腔ケアは重要になる。歯科は歯だけでなく、嚥下(えんげ)(飲み込み)や発声、かみ合わせなど全身の健康につながる治療にも関わっているので、定期的にかかりつけの歯科医院で検査をしてほしい。口の中を清潔に保つことはコロナをはじめとした感染症予防につながる。毎日のケアもしっかり心掛けることも大切だ。歯科治療を原因としたクラスターは発生しておらず、感染対策も徹底しているので、安心して受診してほしい。
―地域や社会にどのように関わっていくか。
2018年に一般の歯科医では対応が難しい障害児・者の治療をする「県口腔健康センター」を大分市の県歯科医師会館に開設した。患者も増えてきていて、必要としている人が多かったことを実感している。ただ、センターのことを知らずに治療を諦めている人もいるとみられるので、普及啓発活動に力を入れたい。事件や事故、災害などの際に歯型から身元を特定する県警嘱託歯科医については、大規模災害でも対応できるよう各地域の歯科医師会とも協力体制を構築したい。
―今後の課題は。
高齢者の口腔ケアは健康寿命を延ばすためにも不可欠だと感じている。私は佐伯市で開業しているが、通院するための交通手段がない患者もいる。これからは歯科医がしっかり地域に出て、支援することも求められている。医科歯科連携も進めており、がん手術前後での口腔ケアでは地域がん診療連携拠点病院と協力体制を築いている。手術前から口のケアに関わることで、術後の患者のQOLを高めていることが分かっている。今後は他の疾患などにも広げて、県民の健康に寄与できればと考えている。
ブラッシングの際の歯磨剤の必要性
歯磨剤(歯磨き粉)の役割は、あくまで歯ブラシの補助です。あまりつけすぎるとスッキリ感が先行して磨けていなくても磨けた気になりますので注意してください。つけるのならほんの少量で大丈夫です。歯磨剤の中には薬効、歯質強化(フッ化物入り)、知覚過敏対応などブラッシングだけでは得られない効果もあるので、正しい使いかたで使用することが大切です。
過去ログ
- 2026年02月 (18件)
- 2026年01月 (31件)
- 2025年12月 (26件)
- 2025年11月 (24件)
- 2025年10月 (26件)
- 2025年09月 (20件)
- 2025年08月 (22件)
- 2025年07月 (21件)
- 2025年06月 (12件)
- 2025年05月 (13件)
- 2025年04月 (5件)
- 2025年03月 (11件)
- 2025年02月 (11件)
- 2025年01月 (13件)
- 2024年12月 (22件)
- 2024年11月 (22件)
- 2024年10月 (20件)
- 2024年09月 (17件)
- 2024年08月 (24件)
- 2024年07月 (16件)
- 2024年06月 (13件)
- 2024年05月 (23件)
- 2024年04月 (17件)
- 2024年03月 (13件)
- 2024年02月 (19件)
- 2024年01月 (16件)
- 2023年12月 (27件)
- 2023年11月 (17件)
- 2023年10月 (14件)
- 2023年09月 (17件)
- 2023年08月 (17件)
- 2023年07月 (16件)
- 2023年06月 (18件)
- 2023年05月 (14件)
- 2023年04月 (16件)
- 2023年03月 (20件)
- 2023年02月 (14件)
- 2023年01月 (12件)
- 2022年12月 (21件)
- 2022年11月 (16件)
- 2022年10月 (17件)
- 2022年09月 (17件)
- 2022年08月 (16件)
- 2022年07月 (15件)
- 2022年06月 (20件)
- 2022年05月 (10件)
- 2022年04月 (14件)
- 2022年03月 (22件)
- 2022年02月 (15件)
- 2022年01月 (17件)
- 2021年12月 (18件)
- 2021年11月 (13件)
- 2021年10月 (24件)
- 2021年09月 (16件)
- 2021年08月 (17件)
- 2021年07月 (20件)
- 2021年06月 (14件)
- 2021年05月 (15件)
- 2021年04月 (20件)
- 2021年03月 (22件)
- 2021年02月 (10件)
- 2021年01月 (10件)
- 2020年12月 (15件)
- 2020年11月 (15件)
- 2020年10月 (16件)
- 2020年09月 (15件)
- 2020年08月 (19件)
- 2020年07月 (15件)
- 2020年06月 (14件)
- 2020年05月 (19件)
- 2020年04月 (12件)
- 2020年03月 (9件)
- 2020年02月 (18件)
- 2020年01月 (14件)
- 2019年12月 (23件)
- 2019年11月 (11件)
- 2019年10月 (15件)
- 2019年09月 (20件)
- 2019年08月 (12件)
- 2019年07月 (19件)
- 2019年06月 (19件)
- 2019年05月 (14件)
- 2019年04月 (11件)
- 2019年03月 (14件)
- 2019年02月 (10件)
- 2019年01月 (5件)
- 2018年12月 (16件)
- 2018年11月 (15件)
- 2018年10月 (15件)
- 2018年09月 (16件)
- 2018年08月 (6件)
- 2018年07月 (32件)
- 2018年06月 (17件)
- 2018年05月 (11件)
- 2018年04月 (24件)
- 2018年03月 (14件)
- 2018年02月 (8件)
- 2018年01月 (17件)
- 2017年12月 (15件)
- 2017年11月 (26件)
- 2017年10月 (22件)
- 2017年09月 (30件)
- 2017年08月 (24件)
- 2017年07月 (14件)
- 2017年06月 (27件)
- 2017年05月 (10件)
- 2017年04月 (23件)
- 2017年03月 (21件)
- 2017年02月 (14件)
- 2017年01月 (31件)
- 2016年12月 (25件)
- 2016年11月 (18件)
- 2016年10月 (17件)
- 2016年09月 (15件)
- 2016年08月 (9件)
- 2016年07月 (10件)
- 2016年06月 (19件)
- 2016年05月 (10件)
- 2016年04月 (13件)
- 2016年03月 (13件)
- 2016年02月 (14件)
- 2016年01月 (15件)
- 2015年12月 (26件)
- 2015年11月 (31件)
- 2015年10月 (31件)
- 2015年09月 (37件)
- 2015年08月 (40件)
- 2015年07月 (37件)
- 2015年06月 (40件)
- 2015年05月 (33件)
- 2015年04月 (33件)
- 2015年03月 (29件)
- 2015年02月 (32件)
- 2015年01月 (27件)
- 2014年12月 (29件)
- 2014年11月 (27件)
- 2014年10月 (31件)
- 2014年09月 (34件)
- 2014年08月 (34件)
- 2014年07月 (35件)
- 2014年06月 (48件)
- 2014年05月 (42件)
- 2014年04月 (38件)
- 2014年03月 (43件)
- 2014年02月 (38件)
- 2014年01月 (37件)
- 2013年12月 (43件)
- 2013年11月 (41件)
- 2013年10月 (44件)
- 2013年09月 (44件)
- 2013年08月 (41件)
- 2013年07月 (33件)
- 2013年06月 (39件)
- 2013年05月 (42件)
- 2013年04月 (28件)
- 2013年03月 (44件)
- 2013年02月 (41件)
- 2013年01月 (48件)
- 2012年12月 (48件)
- 2012年11月 (41件)
- 2012年10月 (42件)
- 2012年09月 (44件)
- 2012年08月 (40件)
- 2012年07月 (41件)
- 2012年06月 (44件)
- 2012年05月 (44件)
- 2012年04月 (41件)
- 2012年03月 (49件)
- 2012年02月 (41件)
- 2012年01月 (43件)
- 2011年12月 (45件)
- 2011年11月 (42件)
- 2011年10月 (49件)
- 2011年09月 (44件)
- 2011年08月 (41件)
- 2011年07月 (43件)
- 2011年06月 (49件)
- 2011年05月 (44件)
- 2011年04月 (41件)
- 2011年03月 (44件)
- 2011年02月 (42件)
- 2011年01月 (44件)
- 2010年12月 (46件)
- 2010年11月 (44件)
- 2010年10月 (48件)
- 2010年09月 (44件)
- 2010年08月 (45件)
- 2010年07月 (47件)
- 2010年06月 (44件)
- 2010年05月 (46件)
- 2010年04月 (43件)
- 2010年03月 (46件)
- 2010年02月 (42件)
- 2010年01月 (42件)
- 2009年12月 (42件)
- 2009年11月 (43件)
- 2009年10月 (41件)
- 2009年09月 (43件)
- 2009年08月 (41件)
- 2009年07月 (44件)
- 2009年06月 (35件)
- 2009年05月 (41件)
- 2009年04月 (46件)
- 2009年03月 (47件)
- 2009年02月 (41件)
- 2009年01月 (43件)
- 2008年12月 (45件)
- 2008年11月 (44件)
- 2008年10月 (43件)
- 2008年09月 (42件)
- 2008年08月 (38件)
- 2008年07月 (41件)
- 2008年06月 (38件)
- 2008年05月 (42件)
- 2008年04月 (41件)
- 2008年03月 (40件)
- 2008年02月 (37件)
- 2008年01月 (42件)
- 2007年12月 (47件)
- 2007年11月 (35件)
- 2007年10月 (40件)
- 2007年09月 (34件)
- 2007年08月 (36件)
- 2007年07月 (31件)
- 2007年06月 (36件)
- 2007年05月 (41件)
- 2007年04月 (22件)
- 2007年03月 (25件)
- 2007年02月 (23件)