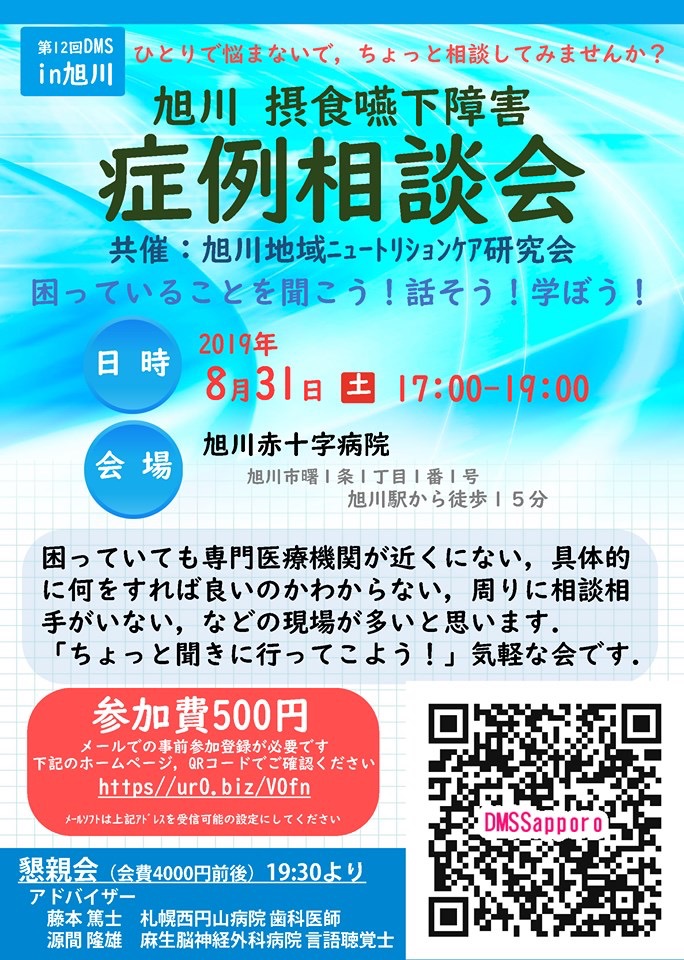お食事をするときは、条件によって味の感じ方にも差がでてきます。
好きなものを食べるときはもちろん、
空腹時や楽しい雰囲だと、さらに美味しく感じますよね。
お口の状態をより良くすることでも、しっかり味わうことができます。
舌や上あごなどには味を感じる細胞(味雷:みらい)がたくさんあります。
舌に白い汚れ(舌苔:ぜったい)が付いていると、
味雷に浸透しにくくなるため、味を感じにくくなります。
お口の中が乾く原因に、唾液の出る量が少なくなっていることがあります。
唾液は食べ物を噛むとたくさん出てきて、食べ物の味を味雷に浸透しやすくします。
つまり、唾液が少ないと食べ物の味を感じにくくなるということです。
唾液は噛むことでさらによく出るようになるので、しっかりと噛める歯と
健康なお口が必要ということになります。
産まれたばかりの赤ちゃんがお母さんのおっぱいを吸うのは本能ですが、
母乳やミルクから、大人と同じ食事を食べられるようになるために、
離乳食という段階を踏み、経験によって食べるということを習得します。
そして、歯の芽(歯胚:しはい)はお母さんのお腹の中にいるときに作られます。
などとお話しすると、味わうためには赤ちゃんのときから気を付けないといけないの?
ってことになりますが・・・。
今できる、さらに美味しくお食事をする方法として、
ゆっくり時間をかけた歯磨きと、舌のお掃除を心がけてみてください。
ゆっくり歯磨きをすることで、サラサラの唾液がたくさん出ます。
そして、ゆっくりたくさん噛んでお食事を味わってください。
▼参考:歯とお口のことなら何でもわかる テーマパーク8020
かむ、食べる、味わう
https://k.d.combzmail.jp/t/sw0d/i028pes0kvskmh3cjbOdB