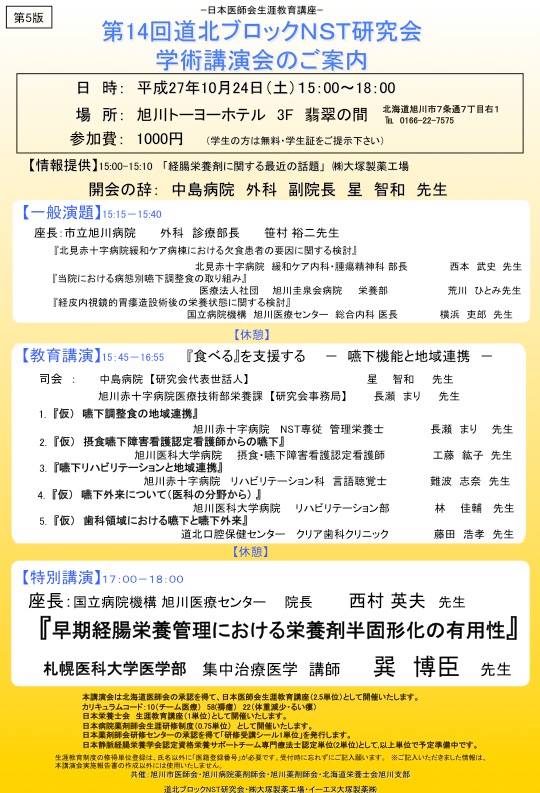岡山大病院(岡山市北区鹿田町)は、がんなどで舌を失った患者が再び会話できるよう支援する「夢の会話プロジェクト」外来を開設した。同大の医学、歯学、工学部が連携して独自に開発した装具を用い、発語を改善する。同病院によると、全国でも珍しい取り組みという。
同外来は今月1日に開設。大学院医歯薬学総合研究科(咬合(こうごう)・有床義歯補綴(ほてつ)学)の皆木省吾教授らが、入れ歯を作る技術を応用し、舌の役割を果たす「人工舌」を作ったのがきっかけ。舌がんを患い、舌の4分の3を切除した同研究科の小崎健一教授が実際に使いながら改良を重ねた。
人工舌は、下あごにはめて舌のように動かせる。従来、上あごに装着して発音を助ける装具はあったが、舌の代わりになるものはなかったという。
今後、工学部で音声をデジタル処理する技術を取り入れ、より明瞭に発音できる装置を作る計画。皆木教授は「症例数を増やして人工舌の普遍的なデザインを確立し、ノウハウを全て公開したい。将来的には脳梗塞による言語障害の患者らの支援にもつなげたい」と話す。
外来は初診(火曜午前)と再診(月曜午後)の週2回。装具の製作からリハビリまで一貫体制で支援する。治療は保険適用になる。
問い合わせは咬合・義歯補綴科にファクス(086―235―6689)かメール(kogo.info@cc.okayama―u.ac.jp)。
●がん宣告された小崎教授 「人工舌」誕生後押し
「夢の会話プロジェクト」を後押ししたのは突然、がんを宣告された研究者の存在だ。
岡山大大学院医歯薬学総合研究科の小崎健一教授(51)。広島大歯学部卒業後、大学病院勤務を経て口腔(こうくう)がんの研究者になった。岡山大に着任して1カ月後の昨年5月。舌がんが見つかった。
「がんを研究する自分がまさか患者になるとは…」。専門家であるがゆえに、自分の置かれた状態がよく分かった。「1年、生きられないかもしれない」。そんな思いもよぎったという。
舌を切除する手術を受けたものの再発。3度に及ぶ手術で、中咽頭や右あごの骨も切除し、その影響で会話や食事が難しくなった。「大学教員は話すことが仕事。しゃべれなければ職場復帰できない」。相談を受けた大学の先輩でもある皆木省吾教授らは温めていたアイデアを基に装具を製作。小崎教授に届けた。何度も試作し「人工舌」が誕生した。
歯科薬理学が専門の小崎教授。がんの新薬開発を目指してきた。「創薬の夢はかないそうにないが、歯科医師、がん研究者、患者という三つの立場を経験した人はそういないはず。その立場でしかできないことを精いっぱいしたい。少しでも誰かの役に立てれば幸せ」。人工舌を使い、かみしめるように話した。