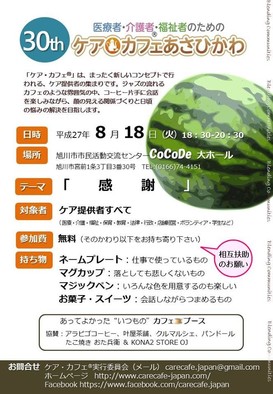自然な見た目の「セラミックス製入れ歯」が好まれるようになり、化学メーカーが素材の生産に力を入れている。特に注目しているのがジルコニアだ。高価格ながら金歯・銀歯の金属製から主役の座を奪いつつあり、高齢化による需要増にも期待する。
東ソーは3日、2017年4月末までに山口、三重両県の工場で、ジルコニアの生産能力を約3割増やすと発表した。いま、最も販売増が見込める入れ歯素材だ。同社が1983年に光ファイバーのコネクター用などとして世界で初めて商業生産化した。入れ歯には00年ごろから欧州で使われ始め、国内でも05年以降、使われている。
金銀並みの強さを持ちながら、自然な風合いを出せる。たばこのヤニなども再現でき、自分の歯と並んでも違和感がない。金属アレルギーの心配もない。保険適用外のため、1本10万~15万円と金属製より1~2割ほど高いが、東ソー広報は「高くてもいいものをと選ぶ人が増えている」と説明する。これまでは主に奥歯で使われてきたが、最近は前歯にも使いやすい素材を開発した。
素材を仕入れて歯科医院向けに入れ歯を成形する事業を持つクラレは、表面の透明性を向上させたジルコニア製の新商品を7月から欧米で発売した。国内でも今秋に売り出す。広報は「材料の変化は世界的な流れ」。同社によると世界でのジルコニア製の市場規模は年約160億円にまで伸びた。年2千億円前後とされる金属製からの入れ替えはさらに進むとみる。
2015年8月5日(水)配信朝日新聞