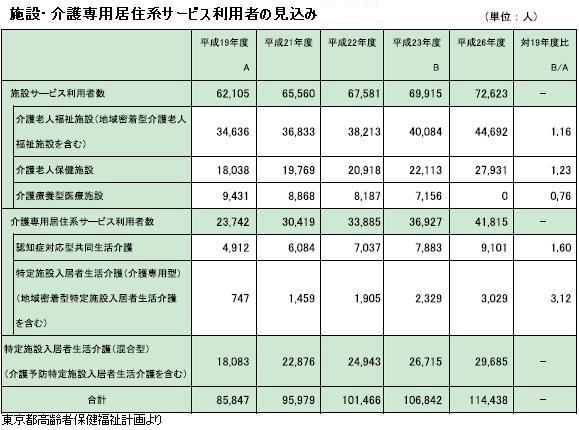食品による高齢者の窒息事故は食品の物性および嚥下する能力の低下が原因で起きます。
高齢期には、のどの筋肉の衰えや唾液の分泌量の減少などにより嚥下機能が低下します。
窒息の原因食品
1.もち 21%
2.ごはん 16%
3.菓子類 14%
4.パン 12%
5.魚介類 10%
6.肉類 9%
6.くだもの類 9%
7.穀物類 7%
8.こんにゃくゼリー 2%
平成19年度厚生労働省特別研究「食品による窒息の現状把握と原因分析」より
窒息事故を防ぐためには、
■食べ物は食べやすい大きさにしてよく噛んで食べる
■食事の際はなるべくだれかがそばにいて注意して見ている
2009.04.12 Sunday 00:11 | comments(0) | - | 歯科(高齢者・介護) | ▲