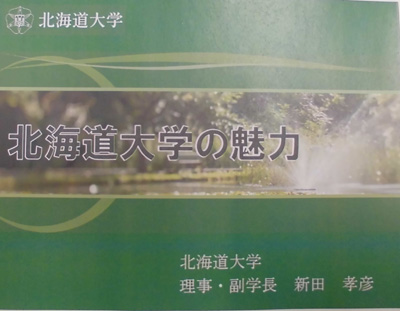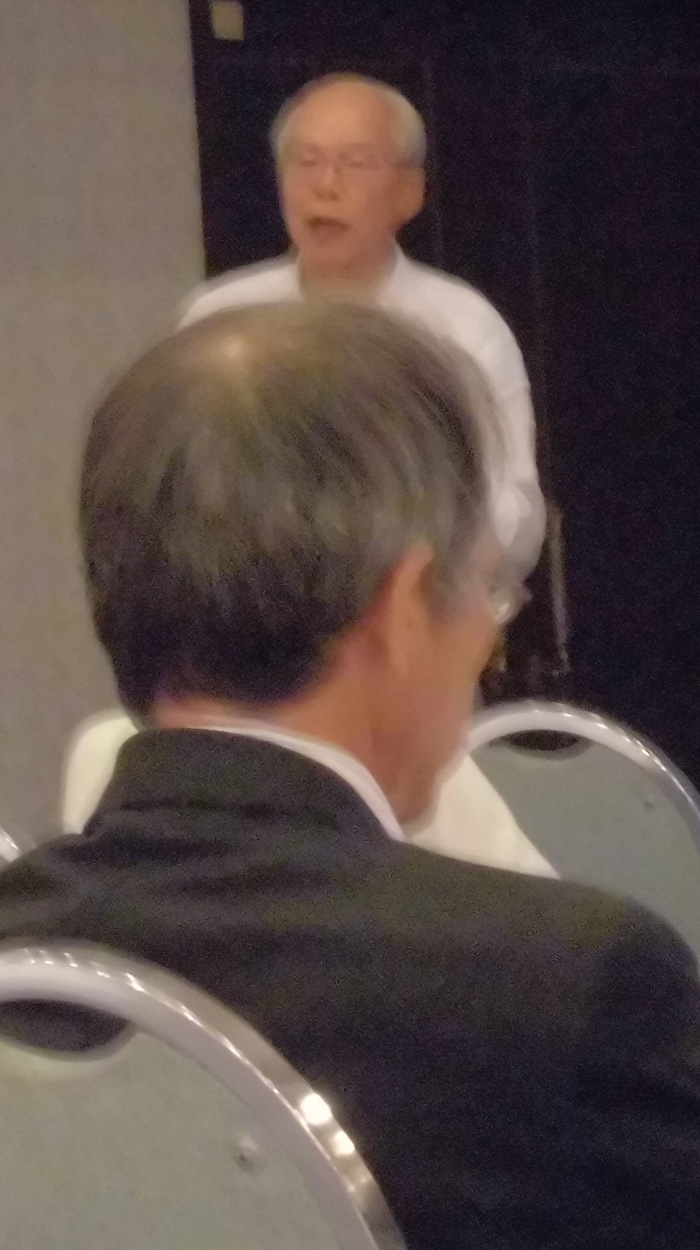日本歯科大学新潟生命歯学部解剖学教室にて頭頸部の解剖と脳の解剖をしました。30年ぶりの解剖で首から顎・頬までの筋肉・血管・神経の走行を実際に見て人間の仕組みの勉強をしました。ここでは見せられませんがご遺体には感謝です。この場を作っていただきました。小樽の館先生ならびに解剖学教授の影山先生には感謝します。
記事一覧
第9回体験型「北大セミナーin旭川」が開催されました。
平成28年9月11日旭川東高にて北海道大学の各学部(医学部、歯学部、薬学部、獣医学部、工学部、法学部、理学部、その他)が学部内の活動状況とセミナーをしました。歯学部は、小児歯科学講座の八若教授が担当で北大の紹介と歯科の実習をしました。道内の高校生の北大離れが続いており、これからも北大の良さをアピールしてほしいです。私は、実習の手伝いとして参加しました。
北海道歯科医師テニスダブルス大会で優勝しました。
8月28日花咲テニスコートで優勝しました。多少なり体力には自信があったつもりでしたが、年齢に勝てませんでした。両足もう少しで痙攣しそうでした。明日からまた朝テニスです。
松田先生から「森伊蔵」を頂きありがとうございました。
認知症をめぐる最新の話題
大学卒業後50年を超えて自分も前期高齢者となり治療される側となったとの冗談から始まった神楽神経科内科医院 白井宏之先生の講演が、トーヨーホテル3階翡翠の間にて開催されました。上記タイトルでの講演は、今までの認知症が学術的に解明されてきていること、生活習慣病との関連性など我々日常生活に関わる内容で大変参考になりました。
講演終了後大田先生のご発声にてビールパーティが開催され多職種での交流があり垣根のない話題に盛り上がりました。演者の白井先生、座長の林先生、懇親会の大田先生ご苦労様でした。
北海道PEGサミットイン小樽
平成28年8月7日PEGサミットイン小樽にて発表しました。タイトルは、「口腔ケアの再考」です。歯ブラシや粘膜の清掃だけではない、お口の機能を高める重要性や嚥下障害のある患者・利用者さんは、汚れをお口からどのように出すか、その後のお口の保湿の重要性などを発表しました。25分の発表を10回繰り返し、体力のいるセミナーでした。
特養にてセミナーしました。
藤島先生の講演に出席しました。
語聴覚療法学科セミナー
嚥下障害と地域連携
~歴史を踏まえて~
講師 藤島一郎(浜松市リハビリテーション病院 病院長)
嚥下障害 症例を通して連携を考える
講師 森脇 元希(聖隷三方原病院リハビリテーション部)
平成28年7月23日午後1時~
上記セミナ―が開催されました。摂食嚥下障害の歴史、取り組みについての講演から始まり地域連携、摂食嚥下の基礎知識、摂食嚥下障害の原因・治療など幅広い講演をして頂きました。日頃の臨床の再確認と今後のリハビリへの対応に参考となりました。
第2回旭川地域歯科医療連携室講習会が開催されました。
6月29日旭川歯科医師会大会議室にて上記講習会が開催されました。演題は、訪問歯科診療の次の一歩でした。連携室から各市内開業歯科医師に訪問診療依頼しますが、訪問診療が少ない先生に対して治療内容、月の訪問回数をどうするか?書類・会計などについて
講習しました。
過去ログ
- 2025年03月 (1件)
- 2025年02月 (2件)
- 2024年12月 (3件)
- 2024年11月 (1件)
- 2024年10月 (4件)
- 2024年09月 (1件)
- 2024年08月 (3件)
- 2024年07月 (1件)
- 2024年06月 (1件)
- 2024年05月 (1件)
- 2024年04月 (3件)
- 2024年03月 (2件)
- 2024年01月 (1件)
- 2023年12月 (4件)
- 2023年11月 (3件)
- 2023年10月 (2件)
- 2023年09月 (1件)
- 2023年08月 (1件)
- 2023年07月 (5件)
- 2023年06月 (1件)
- 2023年05月 (3件)
- 2023年04月 (2件)
- 2023年03月 (4件)
- 2023年02月 (2件)
- 2023年01月 (7件)
- 2022年12月 (1件)
- 2022年11月 (3件)
- 2022年10月 (2件)
- 2022年09月 (5件)
- 2022年08月 (1件)
- 2022年07月 (2件)
- 2022年06月 (2件)
- 2022年05月 (2件)
- 2022年04月 (3件)
- 2022年03月 (5件)
- 2022年02月 (1件)
- 2022年01月 (4件)
- 2021年12月 (4件)
- 2021年11月 (2件)
- 2021年10月 (3件)
- 2021年09月 (1件)
- 2021年08月 (3件)
- 2021年07月 (3件)
- 2021年06月 (5件)
- 2021年05月 (2件)
- 2021年04月 (4件)
- 2021年03月 (3件)
- 2021年02月 (3件)
- 2021年01月 (3件)
- 2020年12月 (2件)
- 2020年11月 (3件)
- 2020年10月 (2件)
- 2020年09月 (1件)
- 2020年08月 (2件)
- 2020年07月 (5件)
- 2020年06月 (1件)
- 2020年05月 (4件)
- 2020年04月 (2件)
- 2020年03月 (1件)
- 2020年02月 (2件)
- 2020年01月 (2件)
- 2019年12月 (1件)
- 2019年11月 (2件)
- 2019年10月 (4件)
- 2019年09月 (3件)
- 2019年08月 (2件)
- 2019年06月 (2件)
- 2019年05月 (3件)
- 2019年04月 (1件)
- 2019年03月 (3件)
- 2019年02月 (4件)
- 2018年11月 (2件)
- 2018年10月 (2件)
- 2018年09月 (3件)
- 2018年08月 (1件)
- 2018年07月 (3件)
- 2018年06月 (2件)
- 2018年05月 (3件)
- 2018年04月 (1件)
- 2018年03月 (1件)
- 2018年02月 (2件)
- 2018年01月 (2件)
- 2017年12月 (3件)
- 2017年11月 (7件)
- 2017年10月 (3件)
- 2017年09月 (5件)
- 2017年08月 (3件)
- 2017年07月 (7件)
- 2017年06月 (3件)
- 2017年05月 (3件)
- 2017年04月 (3件)
- 2017年03月 (5件)
- 2017年02月 (2件)
- 2017年01月 (5件)
- 2016年12月 (1件)
- 2016年11月 (2件)
- 2016年10月 (10件)
- 2016年09月 (1件)
- 2016年08月 (3件)
- 2016年07月 (5件)
- 2016年06月 (6件)
- 2016年05月 (3件)
- 2016年04月 (1件)
- 2016年03月 (1件)
- 2016年02月 (3件)
- 2016年01月 (2件)
- 2015年12月 (3件)
- 2015年11月 (11件)
- 2015年10月 (6件)
- 2015年09月 (6件)
- 2015年08月 (5件)
- 2015年07月 (3件)
- 2015年06月 (8件)
- 2015年05月 (2件)
- 2015年04月 (4件)
- 2015年03月 (4件)
- 2015年02月 (3件)
- 2015年01月 (4件)
- 2014年12月 (2件)
- 2014年11月 (5件)
- 2014年10月 (1件)
- 2014年09月 (8件)
- 2014年07月 (4件)
- 2014年06月 (7件)
- 2014年05月 (3件)
- 2014年04月 (5件)
- 2014年03月 (6件)
- 2014年02月 (2件)
- 2014年01月 (4件)
- 2013年12月 (3件)
- 2013年11月 (7件)
- 2013年10月 (9件)
- 2013年09月 (2件)
- 2013年08月 (6件)
- 2013年07月 (4件)
- 2013年06月 (4件)
- 2013年05月 (5件)
- 2013年04月 (5件)
- 2013年03月 (6件)
- 2013年02月 (4件)
- 2013年01月 (6件)
- 2012年12月 (5件)
- 2012年11月 (6件)
- 2012年10月 (8件)
- 2012年09月 (8件)
- 2012年08月 (6件)
- 2012年07月 (10件)
- 2012年06月 (9件)
- 2012年05月 (8件)
- 2012年04月 (9件)
- 2012年03月 (12件)
- 2012年02月 (6件)
- 2012年01月 (7件)
- 2011年12月 (10件)
- 2011年11月 (9件)
- 2011年10月 (10件)
- 2011年09月 (5件)
- 2011年08月 (4件)
- 2011年07月 (8件)
- 2011年06月 (8件)
- 2011年05月 (5件)
- 2011年04月 (6件)
- 2011年03月 (6件)
- 2011年02月 (8件)
- 2011年01月 (13件)
- 2010年12月 (9件)
- 2010年11月 (7件)
- 2010年10月 (9件)
- 2010年09月 (11件)
- 2010年08月 (5件)
- 2010年07月 (7件)
- 2010年06月 (11件)
- 2010年05月 (9件)
- 2010年04月 (5件)
- 2010年03月 (8件)
- 2010年02月 (9件)
- 2010年01月 (14件)
- 2009年12月 (1件)